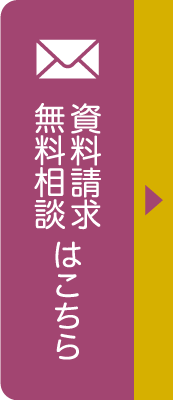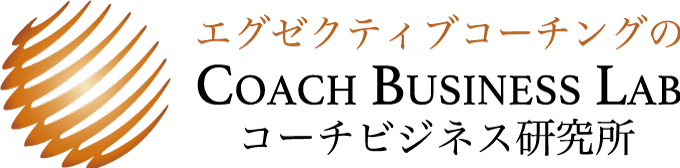私はクリケットのことばかり考えている。どこにいても、心の内には常にあの魅力に満ちたゲームがある。クリケットには、喜び、記憶に残るプレー、ドラマ、追いつ追われつつの複雑なゲーム展開があり、無限の可能性がある。
(『Hit Refresh~マイクロソフト再興とテクノロジーの未来(54ページ)』より引用)
エキサイティングで挑みがいのある未来が到来する!
マイクロソフトの3代目CEOサティア・ナデラ氏の著作『Hit Refresh』を紐解きながら、コーチングを語ってみようと思い立ち、コラムで綴ってきました(野中郁次郎一橋大学名誉教授の紹介を含めると今回で7回目)。同書は、創業者(初代CEO)ビル・ゲイツ氏の4ページの「序文」から始まります。その「推薦文」を前回引用しています。
それは、「……サティア・ナデラがチームに加わると、事態が一変した。かれは謙虚であり、先見の明があり、現実的で、わが社の戦略にもするどい疑問を投げかけた。また、……」という、“ほんの一部”だったのですが、今回、(chapter2)「率いる方法を学ぶ」を取り上げるにあたって、「序文」の最後のところは外せない、と感じています。引用します。
……だからこそ、本書には価値がある。サティアは、こうしたテクノロジーの難しい問題に向き合いながら、テクノロジーが生み出すチャンスを最大限に生かすための道筋を示している。さらに本書には、サティアの興味深い身の上話のほか、文学作品からの引用が予想以上に多く、大好きなクリケットから学んだ教訓も盛り込まれている。
私たちは、来るべき未来に楽観していい。世界はかつてない速さで進歩し、よい方向へ進んでいる。本書は、エキサイティングで挑みがいのある未来への示唆に富むガイドになるだろう。(7ページ)
コーチングは「未来志向」であることを繰り返し語ってきました。『Hit Refresh』は、2017年刊ですから、新型コロナ禍、ロシアのウクライナ侵略、そしてイスラエルのガザ侵攻も起こっていません。ですから、今この時、未来を「ネガティブ」に捉えてしまう環境が世界を覆っていることを、否定できないかもしれません。
私たちは戦争の世紀である20世紀を経て、今ここにいる…
ただし、戦争の世紀(原爆までもが使われたのです)であった20世紀を私たち人類は経験し、語り継いできました。だからこそ、ゲイツ氏の「よい方向へ進んでいる」という、現在なかなか口にできないこの言葉の意味を俯瞰し、受けとめ、信じることこそが求められている、と強く感じるところです。
さて、今回コラムを書くに当たって、「最後のところは外せない」と述べた理由は、「大好きなクリケットから学んだ教訓も盛り込まれている」という言葉に響いたからです。
冒頭の引用は、54ページから始まる(chapter2)「率いる方法を学ぶ」の書き出しです。クリケットへの熱い想いは、11ページにわたって続きます。
ナデラ氏は、マニバル工科大学(学士)を卒業し、米国のウィスコンシン大学に留学するまで、インドで過ごしています。両親、特に母親の影響を受けていることが、伝わってくるのですが、そのこととは別次元で、クリケットに嵌り、クリケットと共に青春があったことが、同書には描かれています。
私は、クリケットについては「名称」くらいしか知らなかったので、新鮮でした。クリケットについて、たびたびYouTubeで視聴していることを、5月1日のコラムで書いています。
サティア・ナデラ氏の青春はクリケットと共にあった!
ナデラ氏は、野球と比較しつつクリケットがビジネス戦略を思索・遂行する上で、いかに有効かを詳述するのですが…
どちらのスポーツも限りなく複雑だが、ここでは得点を多く取ったチームが勝ちだと言っておけば十分だろう。本書はクリケットのルールを解説するためのものではない。ただし、クリケットとビジネスには共通点がある。(55ページ)
ナデラ氏はこのように、スポーツを理解するための入り口であるルールについては触れてくれません。ここで、お節介であることを自覚した上で、クリケットのルールを簡潔に紹介させていただきます。
11人対11人で、楕円型のフィールド(野球場と同等の広いグラウンド)で戦います。その中央に長方形(長辺が約20m)のピッチがあり、その両端に3本の棒(ウィケット)を立てます。
バッター(バッツマン)は後ろにある棒(ウィケット)を守って、当てられないようにするためボールを打ちます。バッターは360度のどこへ打ってもOKです。
得点の入り方は、打った後にバッターとそのペアの人が走り、向かい側に到達すればOKです。
打たれた場合、打者をアウトにするパターンは、野球同様にさまざまあります。
野球のような9回の表裏ではなく、最近の主流は120球を投げて攻守が交代することが多いようです。
どのような世界でもプロフェッショナルのプレーは感動的!
これだけでは、理解は困難ですね(苦笑)
動画解説のほうがわかりやすいと思うので、日本クリケット協会によるYouTubeの視聴をお薦めします。
YouTubeをさまざまチェックすると、プロのファイプレーシーンなども豊富にアップされています。野球もそうですが、プロ選手のプレーは素晴らしい!
躍動するプロ選手の姿を見ながら、私は「オーソリティーはどのようにして誕生するのか?」について、少し考えてみました。
「何か」がきっかけとなって興味を覚え、そのことを調べ始め、自身の価値観にフィットすると、その世界への共感度が高まります。受動的ではない「内発的動機」が起動します。そのプロセスが持続的努力を促し、習慣化することで、いつのまにか「その世界のオーソリティー」になっている…
何ごともすべては「きっかけ」から始まる…
「きっかけ」は、心を寄せる人の言葉、友人の推薦などが思い浮かびます。素晴らしい教師、コーチとの出会いも「大きなきっかけ」です。ノーベル賞受賞者も、スタートはすべて「素人」です。「きっかけ」からすべては始まっていることが理解できますね。
ただ、後に「偉人」となる人は、その「きっかけ」の取り込み方が、並ではないのでしょう。言い換えれば、「圧倒的な感動体験」が途切れることなく、連鎖していったのだと想像します。
「率いる方法を学ぶ」でのナデラ氏が語りは、文学的な表現を交えての、次の言葉が導入です。
当時クリケットに感じていた魅力は、クリケットがあまり盛んではない国に住んでいる今でも、私をとらえて離さない(米国も100年以上前には、定期的にオーストラリア代表チームやイングランド代表チームを呼んで試合をしていた)。私にとってクリケットは、いたるところに伏線が張り巡らされ息をつかせぬ展開を見せるロシアの小説のようなものだ。たった一度の目覚ましい攻撃、あるいはたった3球の巧みなボールで、ゲームの形勢が変わってしまうこともある。
このあまりに短すぎるクリケット人生から学んだ原則は3つある。それは、CEOとして現在も活用しているビジネスリーダーシップの原則と直接関係している。(58ページ)
ナデラ氏が語る「ビジネスリーダーシップ3原則」とは?
ここからナデラ氏は、一つの原則につき1ページを割きながら、クリケットから学んださまざまの事柄が、マイクロソフトCEOという、世界に多大な影響を与えるシゴトを遂行し、全うしていく上で、いかに自身の「拠り所」になっているかを、熱く語ります。
その3つの原則とは…? 最初の1行(のみ)を引用します。
第一の原則は、おじけづき、ためらってしまうような場面でも気迫と熱意で立ち向かうことだ。(58ページ)
第二の原則は、自分個人の成績や評判よりも、チームを第一に考えなければならないということだ。(59ページ)
言うまでもなく、クリケットから学べる教訓や原則は無数にあるが、私にとっての第三の原則は、リーダーシップが極めて重要ということだ。(60ページ)
『Hit Refresh』は翻訳版を読んでいるので、原文は定かではないのですが、小説家のような筆致でナデラ氏の語りは続きます。
この3つの原則それぞれを詳述したいところですが、(chapter2)「率いる方法を学ぶ」の中締めといえる62ページの8行を引用し、今回のコーチング解説を終えることにします。
企業文化に重点を置き、そこから何ができるかを考える!
人生の初めにクリケットから学んだこうした教訓が、私のリーダーシップのスタイルを形づくった。もちろん、夫として、父親として、マイクロソフトの発展の一端を担った若きエンジニアとして、そして、新事業を構築する責任を担う幹部としての経験も生きている。そのリーダーシップスタイルとは、これまで通りのやり方でビジネスを行うのではなく、企業の文化に重点を置き、そこから何ができるかを考えるというものだ。現在のわが社で進行中の変革の素材になるものも、こうした経験の積み重ねから生まれた。つまり、目標とイノベーションと共感、この三つの化学反応に基盤を置くという原則である。
坂本 樹志 (日向 薫)
現在受付中の説明会・セミナー情報
- 新入社員コミュニケーション1日研修 ─コーチングのスキルで学ぶ 報連相力アップ─
- 縦割り組織に悩む経営者・組織開発、人事担当者の皆様へ!「グループコーチングWA」体験会のご案内
- 【開催無料・中小企業経営者限定】できる経営者が選ぶ“壁打ち” エグゼクティブコーチング解説セミナー
- 人生が輝きだす最強のコミュニケーション術 無料講座
- 超入門初級コーチングいろは1DAY(10:00-17:00)セミナー
- ビジネスリーダーのための傾聴1DAYセミナー
- 1on1がうまくいかない・・なんとかしたいと思っているあなたへ上司として自信を取り戻す1on1スキル向上セミナー
- 【2026年2月】コーチング経営アカデミー コーチ養成講座説明会
- 【無料開催・経営者・人事担当者限定】これで会社を変える!社員の自律と成長を促すコーチング活用セミナー