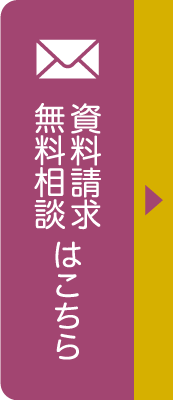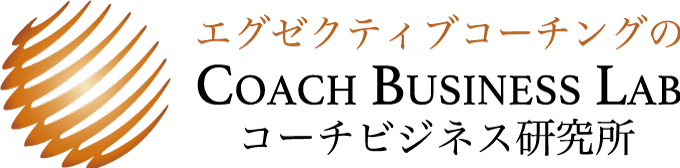マイクロソフトのCEOに就任した後のある日、私は集中治療室を訪れ、医療機器から聞こえてくる小さな作動音やアラーム音に満ちたザインの部屋を見渡した。その時ふと、これらの機器の多くがウィンドウズ上で稼働していること、それらがクラウドに接続される機会がますます増えていることに気づいた。クラウドとは、巨大データストレージや高度なデータ処理能力を備えたネットワークのことで、私たちが現在当たり前のように使っているテクノロジーになくてはならないものだ。その経験を通じて私は、マイクロソフトでの私たちの仕事がビジネスを超えていることをはっきりと悟った。現にその仕事が、か弱い男の子の命を支えている。
(『Hit Refresh~マイクロソフト再興とテクノロジーの未来(63ページ)』より引用)
マイクロソフトのやっていることはビジネスを超えている!
前回のコラムより、『Hit Refresh』の(chapter2)「率いる方法を学ぶ」を取り上げ、コーチングについて語ることを始めています。
この(chapter2)は、「私はクリケットのことばかり考えている。どこにいても、心の内には常にあの魅力に満ちたゲームがある。……」と、マイクロソフト3代目CEOのサティア・ナデラ氏の「クリケット愛」溢れる言葉からスタートします。
(chapter1)「ハイデラバードからレドモンドへ」でも、その「愛」は語られているのですが、(chapter2)のタイトルが「率いる方法を学ぶ」とあるように、現在3兆ドルという世界1の株式時価総額を誇るマイクロソフトを率いる、ナデラCEOのリーダーシップの原則は、インド時代の「クリケット三昧」の日々に培われたことが、しっかりと描かれているのですね。
私は同書を読むまで、クリケットは名称くらいしか認知しておらず、「インドでは妙なスポーツが流行っているんだな…」と、少々失礼なイメージでこのスポーツを捉えていました。ところが…
現在世界最高の経営者とも評価されるナデラ氏が、まるで子供のようにクリケットを語る筆致に感化され、以来You Tubeでアップされている動画を観るようになっています。そうなると、リコメンドされる質量がどんどん増えてくるので、「最初は特別な感情がない場合の方がむしろ好きになっていく、つまり期待していなかった分、好ましい情報をキャッチすると好感情が芽生えていく」という、「対人魅力の心理学」の法則通り、それなりの「クリケットファン」になってきました(笑)
クリケットによって「対人魅力の心理学」を実感した!
前回のコラムでは、ナデラ氏自身が語る「ビジネスリーダーシップ3原則」を引用しています。そして最後に、「企業文化に重点を置き、そこから何ができるかを考える!」と見出しを付し、同書62ページの8行を引用してみました。再掲します。
人生の初めにクリケットから学んだこうした教訓が、私のリーダーシップのスタイルを形づくった。もちろん、夫として、父親として、マイクロソフトの発展の一端を担った若きエンジニアとして、そして、新事業を構築する責任を担う幹部としての経験も生きている。そのリーダーシップスタイルとは、これまで通りのやり方でビジネスを行うのではなく、企業の文化に重点を置き、そこから何ができるかを考えるというものだ。現在のわが社で進行中の変革の素材になるものも、こうした経験の積み重ねから生まれた。つまり、目標とイノベーションと共感、この三つの化学反応に基盤を置くという原則である。(62ページ)
これまで通りのビジネスのやり方を行なうのではなく……
さて、冒頭に引用したのは、上記の後に綴られるナデラ氏の言葉です。長男ザイン氏の誕生によって、ナデラ氏、そして妻のアヌ氏の人生は激変します。
『Hit Refresh』を読み込みコーチングを語るコラムは、今回が8回目なのですが、4月24日にアップした3回目は、「この『Hit Refresh』というナデラ氏の早すぎる自伝(マイクロソフトCEO就任の3年後である2017年に発刊)は、ザイン氏を想い書かれたのかもしれない…」という主旨で、描いています。(chapter1)の内容です。ザイン氏は2022年6月に亡くなります。
(chapter2)では、ザイン氏の存在は、マイクロソフトCEOという世界に多大な影響を与える職責の遂行に、密接不可分であることが語られています。
「わが社は、社会に対してどのような役割を帯び、どのようなかたちで社会に貢献し、人々から喜ばれる存在としてあり続けることができるのか?」
CEOを筆頭に、その会社に所属する人々が悩み、考えることとして、最も崇高なテーマであると考えます。
冒頭の引用の続きです。
そう考えると、わが社のクラウドやウィンドウズ10のアップグレードに関する今後の判断も、これまでにない重要性を帯びることになる。私はその時、この点を肝に銘じなければならないと思った。
息子の状況に対処するには、私が両親から学んだアイデアの探求心や共感能力を日々発揮する必要がある。私はこれを、家庭でも職場でも実践している。ラテンアメリカ、中東、あるいは米国のスラム街の人々に会う時には、相手の考えや気持ち、意見をいつも理解しようと努めている。共感能力の高い父親であること、相手の心の奥底にあるものを発見したいという気持ちを抱くこと、それがリーダーとしての資質を向上させる。(64ページ)
「共感能力」を磨き、相手の奥底にあるものを発見したい!
現在のIT環境を語る上で、クラウドは「基本のキ」ともいえるキーワードですが、ナデラ氏は「病院や学校、企業、研究機関も“パブリック・クラウド”を頼りにしている」と、「公共」の概念を包含するクラウドに触れます。
パブリック・クラウドとは、公的ネットワークを通じてアクセス可能で、プライバシーが保護された大規模コンピューターやデータサービスの集まりを指す。クラウド・コンピューティングのおかげで、膨大な量のデータを分析して、そこから具体的なアイデアや情報を引き出すことが可能になった。つまり、これまでの当て推量や憶測が、データに基づく予測に置き換わった。これは、人間の生活や社会を変える力を秘めている。
私はCEOとして世界中を旅し、共感とテクノロジーが相互に作用しあっている例を幾つも見た。(65ページ)
ここから「例えば…」と、世界中の「共感とテクノロジーが相互に作用しあっている例」が6つほど、具体的に紹介されます。項目だけを列挙してみましょう。
「テクノロジー」と「共感」は相互に作用している!
(事例1)
ナデラ氏が生まれたインドのアーンドラ・プラデーシュ州、現在暮らしている米国ワシントン州タコマなど、学校がクラウド・コンピューティングを利用して、大量のデータを分析し、中退率の改善に役立てている。
(事例2)
ケニアのある新興企業が、モバイル・テクノロジーとクラウド・テクノロジーを活用して、1日2ドル未満で暮らす人々に太陽光発電装置を貸し出す事業を展開している。
(事例3)
ギリシャの大学ではクラウド・データを活用し、消防機関と協力して山火事の予測・防止に取り組んでいる。
(事例4)
スウェーデンでは、研究者がクラウド・テクノロジーを使い、早い段階で正確に読字障害(ディスレクシア)の子どもを発見できるようにしている。
(事例5)
日本では、全国に設置されている数百ものセンサーからクラウドソーシングにより集めたデータをもとに、福島第一原子力発電所から出る放射線を監視し、食品や移動の安全性の確保に役立てた。
(事例6)
ネパールでは、2015年4月に巨大地震が発生した際、国連の災害救助隊はパブリック・クラウドを利用して学校や病院、家庭に関する膨大なデータを収集・分析し、災害補償や支援物資などが迅速に行き渡るようにした。
ナデラ氏は、「物書き」としてもすぐれた能力を有した人であることが伺われます。2015年のシルヴェスター・スタローンの映画『ロッキー』シリーズの『クリード チャンプを継ぐ男』にあったシーンを、挿入します。引用してみましょう。
「雲(クラウド)って何だ?」
ロッキーが自分の教え子のトレーニングメニューを紙にメモする。すると教え子は、スマートフォンでそのメモを写真に撮ると、そのままランニングに行ってしまう。ロッキーは叫ぶ。
「紙はいらないのか?」
すると教え子は答える。
「ちゃんとここにあるよ。クラウドにアップしておいたから」
年老いたロッキーは空を見上げる。
「雲(クラウド)で何だ?」
ロッキーはクラウドを知らないかもしれないが、何百万人という人がそれを利用している。(68ページ)
クラウド・サービスの現在は、「アマゾン」と「マイクロソフト」が世界の双璧ですが、同書が出版されていた2017年頃はどうであったのか… 興味を覚えたので、「2023年のクラウド・サービス アマゾンとマイクロソフト」と、ググってみました。
トップに出てきたのが「クラウドインフラのシェア、AWSが足踏みの一方、マイクロソフトが順調に拡大中」でした。
2018年の世界シェアは、アマゾンが34%程度、マイクロソフトが15%台となっています。それが2023年になると、アマゾンの31%に対して、マイクロソフトが26%と肉薄しています。
『Hit Refresh(翻訳版)』の出版元である「日経BP社」が、同書の帯に記したメッセージは「哲学的信念と共感経営でマイクロソフトを復活させたインド人CEOサティア・ナデラとは何ものか?」です。CEOに就任してほぼ10年、ナデラ氏とは、文字通り「有言実行」の人でした。
次回は「クラウドの誕生(単純な理由?)」から紐解いてみます!
同書の68ページからは、2008年から2017年までのマイクロソフトの格闘が、数十ページにわたって、熱い筆致で語られます。今回のコラムの最後に、その導入の7行を引用して、次回につなげたいと思います。
2008年、マイクロソフトに暗雲が立ちこめていた。生命線であるパソコンの出荷台数は頭打ちになっていた。しかし、アップルやグーグルはスマートフォンやタブレットの売上を伸ばし、マイクロソフトが太刀打ちできない検索やオンライン広告で収益を増やしていた。またアマゾンは、アマゾンウェッブサービス(AWS)を静かに立ち上げたが、そこには、収益が見込める急成長中のクラウド・サービス事業の地歩を固めリードしようという狙いがあった。
クラウドが誕生した背景には、やむにやまれぬ単純な理由があった。……(68ページ)
坂本 樹志 (日向 薫)
現在受付中の説明会・セミナー情報
- 新入社員コミュニケーション1日研修 ─コーチングのスキルで学ぶ 報連相力アップ─
- 縦割り組織に悩む経営者・組織開発、人事担当者の皆様へ!「グループコーチングWA」体験会のご案内
- 【開催無料・中小企業経営者限定】できる経営者が選ぶ“壁打ち” エグゼクティブコーチング解説セミナー
- 人生が輝きだす最強のコミュニケーション術 無料講座
- 超入門初級コーチングいろは1DAY(10:00-17:00)セミナー
- ビジネスリーダーのための傾聴1DAYセミナー
- 1on1がうまくいかない・・なんとかしたいと思っているあなたへ上司として自信を取り戻す1on1スキル向上セミナー
- 【2026年1月、2月】コーチング経営アカデミー コーチ養成講座説明会
- 【無料開催・経営者・人事担当者限定】これで会社を変える!社員の自律と成長を促すコーチング活用セミナー