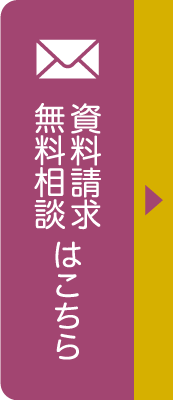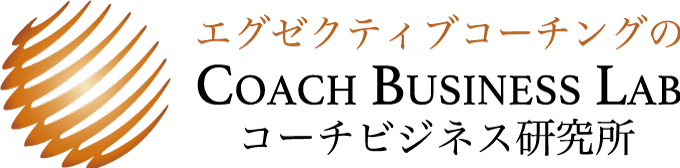研修の在り方の変化
企業内研修と聞くと、多くの人が「講師が教え、受講者が学ぶ」という構図を思い浮かべます。マニュアル化されたスキルや知識を効率的に伝えるこの形式は、高度成長期の日本において確かに有効でした。しかし、今日の企業環境は大きく変わりました。変化が激しく、正解が存在しない時代において、「教わること」だけでは対応しきれなくなっています。むしろ、「自ら問いを立て、学び続ける力」が組織の生命線になりつつあります。
かつては「研修=インプットの場」でした。ところが今、先進企業ほど「研修=変容の場」と捉え始めています。知識を詰め込むのではなく、参加者自身が内省し、自分の価値観や行動パターンを見つめ直す時間。そこでは“正解”よりも“意味”が問われます。
講師が答えを与えるのではなく、参加者同士が対話を通して気づきを得る。まさにコーチング的アプローチが求められる所以です。
例えばあるメーカーでは、管理職研修を従来の講義型から「コーチング・ダイアログ型」に切り替えました。最初は戸惑いの声もありましたが、半年後には「部下との対話が深まった」「自分の思考パターンに気づいた」といった内省的な変化が次々と報告されました。興味深いのは、研修の満足度ではなく、持続する行動変化が明確に見られたことです。これは、学びが「外から与えられた情報」ではなく「自分の中から生まれた気づき」であった証拠です。
コーチング型研修による組織変革へ
研修の目的は、もはや“知識を得ること”ではなく“行動を変えること”にあります。
そして行動の変化は、「自分がなぜそうするのか」を理解する内省からしか生まれません。コーチングはまさにそのプロセスを支える技術であり、文化です。問いを通して自己理解を促し、思考と感情の整合性を回復させ、主体的な行動を引き出す——これが今後の企業研修に不可欠な要素です。
これまでの研修は「講師中心」でした。これからは「学習者中心」。その違いは単に形式の問題ではなく、組織文化そのものの転換を意味します。コーチング型研修とは、社員一人ひとりが“自らの成長を引き受ける主体”になる場を創ること。そこには、「正解を教える人」と「指示を待つ人」という上下関係は存在しません。共に学び、共に成長するパートナーシップが生まれます。
コーチングが企業研修の中核に据えられるとき、研修は単なる「教育コスト」ではなく「組織変革の投資」へと変わります。問いを通して人が変わり、人が変わることで組織が変わる。これこそが、これからの学びのパラダイム転換の本質なのです。
株式会社コーチビジネス研究所(CBL)は、エグゼクティブコーチの養成を行っているコーチング専門機関です。東京都や内閣府、JICA、航空大学校など公的機関でも多くの実績があります。個別コーチングのみならず、組織コーチングにも取り組んでおり、特に独自に開発した「グループコーチングWA」は、いま多くの企業で導入が進んでいます。詳しくは下記をご覧ください。
詳しくはこちら:グループコーチングWA
国際コーチング連盟認定マスターコーチ(MCC)
日本エグゼクティブコーチ協会認定エグゼクティブコーチ
五十嵐 久
現在受付中の説明会・セミナー情報
- 新入社員コミュニケーション1日研修 ─コーチングのスキルで学ぶ 報連相力アップ─
- 縦割り組織に悩む経営者・組織開発、人事担当者の皆様へ!「グループコーチングWA」体験会のご案内
- 【開催無料・中小企業経営者限定】できる経営者が選ぶ“壁打ち” エグゼクティブコーチング解説セミナー
- 人生が輝きだす最強のコミュニケーション術 無料講座
- 超入門初級コーチングいろは1DAY(10:00-17:00)セミナー
- ビジネスリーダーのための傾聴1DAYセミナー
- 1on1がうまくいかない・・なんとかしたいと思っているあなたへ上司として自信を取り戻す1on1スキル向上セミナー
- 【2026年1月、2月】コーチング経営アカデミー コーチ養成講座説明会
- 【無料開催・経営者・人事担当者限定】これで会社を変える!社員の自律と成長を促すコーチング活用セミナー