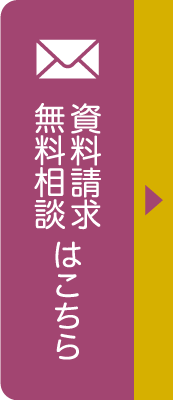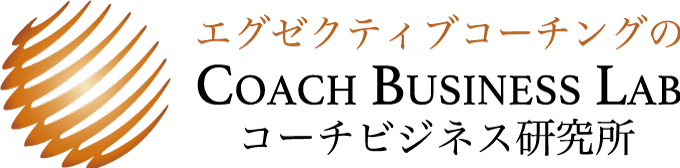米西部ワシントン州シアトル近郊レドモンドの本社で開いた発表会で、サティア・ナデラ最高経営責任者(CEO)は「『ウィンドウズ95』が誕生して約30年がたち、最も高速でAIに対応したウィンドウズPCが誕生した」と話した。
(日本経済新聞2024年5月21日1面「生成AI特化型PC~マイクロソフト、アームと新半導体 処理性能20倍~」より引用))
世界No.1の巨人、マイクロソフトが動き出した!
『Hit Refresh~マイクロソフト再興とテクノロジーの未来』を紐解きながら、コーチングの解説を重ねています(今回で10回目)。
同書のコンセプトは「共感の経営」であり、エグゼクティブコーチングを展開する弊社にとって、「強い援軍を得た!」との思いで、「サティア・ナデラCEOの哲学的信念」の解明に挑戦しています。
先日、「エヌビディアの株式時価総額が世界第2位に躍り出た」と、新聞紙上を騒がせましたが、第1位は、これまで同様にマイクロソフトです。
ただし、話題性という観点では、他の「ファビュラス4」のエヌビディア、アマゾン、メタと比べて、新聞紙上を賑わせる戦略発表は、それほど多くはなかったと振り返っています。それが、冒頭で引用した記事は、「巨人がいよいよ動く!」といわんばかりの、取り上げ方です。
日経新聞は追加記事として翌日5月22日に、「マイクロソフト<爆速経営>に規制の影~AIや端末、寡占指摘リスク」というタイトルを付し、盤石な戦略の内容を活写しています。もっとも日経新聞はバランスを意図したのか、最後当たりで次のようにコメントしています。
盤石とも思える戦略の一方で、懸念材料となるのが規制だ。欧州連合(EU)はマイクロソフトのオープンAIとの提携がEUの合併規制の調査対象になるかどうか検討していると発表。ミストラルとの提携も各国当局で競争法上の懸念が浮上したと報じられている。
M&Aではなく提携戦略でパートナーシップの拡大にまい進!
ナデラCEOは、ビル・ゲイツ氏の「帝国化」とは異なる戦略を志向しているようです。それはM&Aではない「提携戦略」です。それを物語る発表が飛び込んできました(6月11日の日経新聞夕刊1面)。大見出しは「チャットGPT iPhone搭載~アップル、AI開発遅れで連携」です。
「オープンAI」は、あくまでもサム・アルトマンCEOの会社であり、マイクロソフト(サティア・ナデラCEO)は「後方支援」に徹している印象です。もっとも、スーパーコンテンツの「チャットGPT」は、自社製品の「Microsoft Copilot」に全面的に取り込みます。
マイクロソフトは、「ウィンドウズ95」の発売以降、2000年代初頭にかけて「マイクロソフト帝国」を築きます。創業者(初代CEO)のビル・ゲイツ氏の戦闘的経営が背景です。その戦略の根幹は、オペレーティングシステム(OS)である「ウィンドウズ」のセット販売(抱き合わせ販売)でした。帝国たる根拠は、世界中のPCは「ウィンドウズがなければ動かない」、とまで言われた状況をつくり出したことです(MacやLinuxもそれなりの存在感を示していましたが…)。ただし、時代は激変します。スマホの登場です。
アップル、グーグル、そしてメタ。そしてクラウドに関しては、アマゾンが先鞭をつけます。PC完結型で世界を制覇したマイクロソフト帝国は、一転「過剰適応」の陥穽に囚われてしまうのです。ビル・ゲイツ氏からCEOを引き継いだスティーブ・バルマー氏の時代です。
前回の「AGIは実現するのか? …サティア・ナデラCEOは2019年の<チャットGPT-2>に未来を予感し、2024年5月の<チャットGPT-4o>に結実した!」は、コンサルティング的なコラムとして書いてみました。今回は立ち戻って、前々回の「ロッキーは空を見上げてつぶやいた、『雲(クラウド)って何だ?』…アマゾンを猛追するマイクロソフトのクラウド・サービス!」の続編として、コーチングを解説してみようと思います。
ナデラ氏は、2008年の状況を次のように振り返っています。
マイクロソフト帝国は“崩壊一歩手間”の状況にあった…
こうした状況すべてが、マイクロソフトを苦しめた。2008年の大不況の前からすでに、株価は下降を始めていた。さらにその年には、かねての計画通り、ビル・ゲイツがビル&メリンダ・ゲイツ財団の仕事に専念するためマイクロソフトを去った。去ろうとしていたのはビルだけではなかった。(70ページ)
ビル・ゲイツ氏とともに「帝国」を築き上げてきた大物も去ります。
さて、5月8日にアップしたコラムで、ナデラ氏のメンターはスティーブ・バルマー氏であることを書いています。『Hit Refresh』で、スティーブ・バルマー氏が最初に登場したシーンです。再掲します。
入社して間もなく、私は初めてスティーブ・バルマーに会った。スティーブは私の職場に立ち寄り、サンを離れてマイクロソフトに入ってくれたことを称え、実に表現力豊かなハイタッチをしてくれた。以降、スティーブとは、長年にわたり興味の尽きない楽しい会話を繰り返すことになった。当時のマイクロソフトは、ミッションとエネルギーに満ちあふれていた。可能性は無限大だった。(47ページ)
ナデラ氏が、マイクロソフトに入社したのは、1992年です。「ウィンドウズ95」の発売に向けて、会社が一丸となっていたタイミングだったと想像します。そのときのCEOは、もちろんゲイツ氏です。
バルマー氏がマイクロソフトの二代目のCEOに就任するのは2000年1月ですから、その頃のバルマー氏は、まだ「とっても偉いポジション」ではなかったということですね(笑)
ここで、バルマー氏のプロフィールをWikipediaから抜粋してみましょう。
二代目CEOのスティーブ・バルマー氏は、いかなる人物なのか?
ミシガン州デトロイトに生まれる(1956年3月24日)。
父はスイスからのドイツ系ユダヤ人移民で、フォード・モーターにマネージャーとして勤務した。母はベラルーシのピンスク出身の両親を持つ東欧系ユダヤ人移民二世。
高校時代にSATの数学で800点満点を得点するなど数学に秀でた才能を発揮し、1973年に4.0のGPAで卒業、クラスの卒業生総代となる。卒業後はハーバード大学へ進む。
ゲイツ氏は、ハーバード大学を中退し、マイクロソフトを起業します。
ハーバード大学の敷地内には学生寮も立ち並んでいます。その一角に、設立者のジョン・ハーバード氏のブロンズ像があります。
私事ですが、2000年代の初めに「米国の経営およびマーケティングを学ぶ」という主旨のツアーに参加した時のことを思い出しました。全行程は2週間で、強行軍で米国の隅々を視察しています(フロリダ半島南端から、オーバーシーズ・ハイウエイのセブンマイルブリッジを経由してキーウエストにも行っていますから)。
ボストンでは、MITと、このハーバード大学の研究室を訪ねています。「ハーバード氏の銅像の足に触れると幸運が訪れる」と聞いていたので、ツルツル光っている靴の先をしっかり磨いてきました。
「ゲイツ氏とバルマー氏はハーバード大学の学生寮で同室だった」、とあります。ゲイツ氏が「親交を深め合った」親友のバルマー氏を、自分の後を継ぐCEOに指名した理由が、理解できたような気がしています。
バルマー氏とゲイツ氏はハーバード大学で共に学んだ親友同士
プロフィールの続きです。
スタンフォード大学経営大学院の経営学修士課程(MBA)へ進学したが、ゲイツに説得され中退する。
1980年、ゲイツが初めて採用したビジネスマネージャー(事業担当管理職)としてマイクロソフトへ入社、マイクロソフトの30人目の従業員となる。
半世紀の歴史を刻む「IT企業の老舗の中の老舗」たるマイクロソフトにあって、CEOは3人しか存在しません。ゲイツ氏、バルマー氏、そして現在そのポストにあるナデラ氏(就任して10年を迎えました)です。創業者が偉大すぎると二代目はとても苦労する、というのは「世の習い」ですが、バルマー氏がCEOであった14年間(2000年1月~2014年2月)は、まさに、その「ならわし」が指摘されます。ただし、(株)コーチビジネス研究所は「バルマー氏はとても偉大な人物だった」と、再定義します。
「経営トップにとって最も重要な仕事は何か?」と訊ねられたら、皆さんは何と答えるでしょうか? 弊社見解は「後継者を見出し、後継者を育成する」です。ナデラ氏の自伝である『Hit Refresh』には、そのことが「いきいきと」綴られています。
ある日、話があると言って私を呼び出した。オンライン検索・広告事業のエンジニアリングの責任者になってほしいという。後にBing(ビング)として結実することになる事業である。それは、クラウドを利用した、マイクロソフトの最初期の事業の一つだ。(中略)
消費者にも広告主にもそのようにサービスを提供するには、高度な技術が必要でコストもかかる。しかもマイクロソフトの検索分野の市場シェアは低迷していた。それでもスティーブがその分野への投資を決めたのは、マイクロソフトにとって、優れたテクノロジーを構築し、ウィンドウズやオフィス以外の分野で競争力をつけることが必要で、そこにこそ未来があると考えていたからだ。アマゾンが拡大しているクラウド事業に対抗するには途方もないプレッシャーを覚悟しなければならない。だがスティーブは、その事業を私に託したいと言う。(71ページ)
現在における世界のクラウド事業については、アマゾンとマイクロソフトが双璧です。ところが、バルマー氏が「クラウド事業」をナデラ氏に託した時期は、「世界のクラウド・サービスは、アマゾンのAWS!」というブランドイメージが、既に確立していました。
CEOは、全社人事権という最強の権限を有した存在です。ここで読者の皆さんは、シミュレーションしてみてはいかがでしょうか。ご自身は会社のトップ、あるいは経営層の一人です。多大な資金を必要とする新規事業を、目をかけていた部下に命じます。さて、最初に「どのようなことば」をかけますか?
バルマーCEOの場合は…
「だが、よく考えた方がいい。これが君のマイクロソフトでの最後の仕事になるかもしれない。失敗すれば、パラシュートはないからね。墜落するしかない」。私は当時、それが悪い冗談なのかそのままの意味の警告なのかわからなかった。いまだにどちらかわからない。(72ページ)
ナデラ氏は、即答しなかったようです。
ナデラ氏にチャンスを与え、その運命を変えたのはバルマーCEO
私はそれまで、コンシューマー向けの事業に携わったことがなく、マイクロソフトがこれまで行ってきた検索エンジンへの取り組みや、クラウド・インフラ構築の初期の試みについて、ほとんど何も知らなかった。そこである晩、職場での長い1日を終えた後に、第88棟に立ち寄ってみることにした。そこには、インターネット検索のエンジニアリング・チームがいる。責任者になるよう求められているチームに共感するには、現場の廊下を歩いて、どんな人がいるのか確かめてみるのが一番いい。時間は午後9時頃だったが、駐車場はぎっしり埋まっていた。残業を終えて帰ろうとしている社員が数人いるだけだろうと思っていたが、実際にはチーム全員が席につき、テイクアウトの食事をとりながら仕事をしていた。私は誰とも話をしなかったが、自分が目にした光景に驚かずにはいられなかった。彼らはどうしてこんなに働くのか。第88棟では何か重大なことが起きているに違いない。(73ページ)
この続きを、今回のコラムの最後として引用します。バルマーCEOは、偉大な上司であると同時に、ナデラ氏にとっての「かけがえのないメンター」であることが、しっかりと伝わってきました。
その夜のチームの熱心な仕事ぶりを見て、心は決まった。私はスティーブに「わかった。引き受けるよ」と言った。私のパラシュートは何色だったのだろうか。そのパラシュートはもうない。
私は思いがけず新たな世界に入ろうとしていた。そこが、将来のリーダーシップのための、そしてマイクロソフトの将来のための試験場になるとは、当時は思いもしなかった。(73ページ)
坂本 樹志 (日向 薫)
現在受付中の説明会・セミナー情報
- 新入社員コミュニケーション1日研修 ─コーチングのスキルで学ぶ 報連相力アップ─
- 縦割り組織に悩む経営者・組織開発、人事担当者の皆様へ!「グループコーチングWA」体験会のご案内
- 【開催無料・中小企業経営者限定】できる経営者が選ぶ“壁打ち” エグゼクティブコーチング解説セミナー
- 人生が輝きだす最強のコミュニケーション術 無料講座
- 超入門初級コーチングいろは1DAY(10:00-17:00)セミナー
- ビジネスリーダーのための傾聴1DAYセミナー
- 1on1がうまくいかない・・なんとかしたいと思っているあなたへ上司として自信を取り戻す1on1スキル向上セミナー
- 【2026年2月】コーチング経営アカデミー コーチ養成講座説明会
- 【無料開催・経営者・人事担当者限定】これで会社を変える!社員の自律と成長を促すコーチング活用セミナー