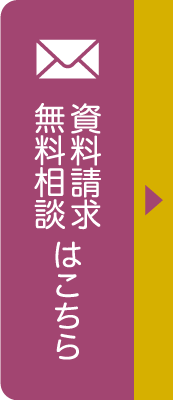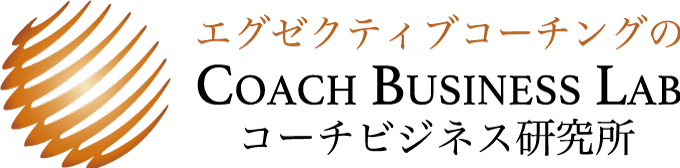クラウドが登場した背景には、やむにやまれぬ単純な理由があった。1980年代には、マイクロソフト、インテル、アップルなどに牽引されてパソコン革命が起き、世界中の家庭やオフィスでコンピューターが利用されるようになった。1990年代になると、フロッピーディスクではなくネットワークを通じてデータを共有したいと考える何百万ものユーザーのニーズに応えるため、クライアント/サーバー時代が到来た。
(『Hit Refresh~マイクロソフト再興とテクノロジーの未来(69ページ)』より引用)
サティア・ナデラCEOが指摘する「クラウド誕生の理由」とは?
前回のコラムの最後に、「次回は、クラウドの誕生(単純な理由?)から紐解いてみます!」と見出しを付していますから、予告通り、サティア・ナデラ氏が指摘するその理由から、今回のコラムを始めてみようと思います。
『Hit Refresh』は、ナデラ氏がマイクロソフトのCEOに就任して3年を経た2017年に出版されています。「自伝」と銘打っての書籍ですから、ナデラ氏が生まれ育ったインドから、そのストーリーは語られます。
インドのマニバル工科大学(学士)を卒業後、米国のウィスコンシン大学(修士)に留学。画像処理とコンピューター・アーキテクチャ、そしてLIPS(長い歴史を持つプログラミング言語)の講座を取ったことで、ITエンジニアとしてのキャリアがスタートします。
ナデラ氏は、ウィスコンシン大学を卒業した1990年にシリコンバレーにあるサンマイクロシステムズに就職しますが、ある日、ワシントン州レドモンドのマイクロソフト本社から突然電話がかかってくるのです。1992年のことでした。
ナデラ氏がマイクロソフトのCEOに就任したのは2014年です。米国(特にIT業界)では珍しい生え抜きのトップであり、渡り歩いて、マイクロソフトのトップにポストを得たCEOではありません。『Hit Refresh』が「マイクロソフト愛」に包まれている理由を、筆者はそこに見出しています。
そしてこの本は、日本の失われた30年と同時代の、米国(つまり世界)のIT業界の激動の歴史が、活写されているのです。冒頭の引用は、その始まりです。「クライアント/サーバー時代」は懐かしい響きですね。続きを引用します。
アマゾンは劇的なコストダウンで業界地図を塗り替えた!
しかし、データは増加の一途をたどり、そのうえアマゾンやオフィス365、グーグル、フェイスブックといった企業やサービスが登場したことで、サーバーの保守コストの増加ペースが、サーバーの能力が向上するぺースを上回ってしまった。そこへクラウド・サービスが出現したことで、コンピューター活用の経済性はがらりと変わった。クラウド・サービスは標準化されており、コンピューター資源を1カ所に集め、かつては手作業で行っていた保守作業を自動化している。さらに、ユーザー自身の手で柔軟に規模の拡大・縮小ができ、使った分だけ支払えばいい。クラウドのプロバイダーは世界中に巨大なデータセンターを設立し、それを低コストでユーザーに貸し出した。これがクラウド革命である。(69ページ)
パラダイムチェンジです。劇的なコストタウンによって、業界の地図が塗り替えられます。アマゾンはITを積極的に活用し、企業規模を拡大していましたが、本来は「通販の会社」です。ところが現在は、クラウド・サービスをコアとする、バリバリの「ITサービスを提供する企業」という業態で語られることも多くなりました。
アマゾンはいち早く、AWSでクラウドをビジネス化した。彼らは早い段階から、書籍や映画などの小売製品を販売するために自社で使用しているクラウド・インフラが、他社の業務にも役立つことを理解していた。そして、各社が自前でクラウドを構築するよりもはるかに安い価格で、そのインフラを少しずつ他社に貸し出せばいいことに気づいていた。2008年6月時点で、アマゾンには、クラウド・プラットフォーム向けにアプリケーションやサービスを構築するデベロッパーが18万人いた。一方マイクロソフトには、商業的に利用できるクラウド・プラットフォームがまだ存在していなかった。(69ページ)
「2008年」というと、皆さんは何を思い浮かべるでしょうか?
1929年の世界大恐慌以来の大不況となる年です。9月15日に、投資銀行のリーマン・ブラザーズ・ホールディングスが66兆円(当時の為替レートで換算)という、とんでもない負債を抱え破綻するのです。私たち日本人にもリアルな記憶として刻まれました。
ナデラ氏は、マイクロソフトの2008年を次のように描写しています。
こうした状況すべてが、マイクロソフトを苦しめた。2008年の大不況の前からすでに、株価は下降を始めていた。さらにその年には、かねての計画通り、ビル・ゲイツがビル&メリンダ・ゲイツ財団の仕事に専念するためマイクロソフトを去った。(70ページ)
ゲイツ氏は「マイクロソフトは終わった」と実感した…?
ここの表現については、ナデラ氏はゲイツ氏に少し気を遣っている印象です。ゲイツ氏が作り上げたマイクロソフト帝国は、ゲイツ氏自身がその終焉を実感したのだと思います。
さて、『Hit Refresh』を取り上げ、コラムで紹介することを始めていますが(今回で9回目)、その視点は「コーチング」であり、同書の「哲学的信念と“共感経営”でマイクロソフトを復活させたインド人CEOサティア・ナデラとは何者か?(同書の帯)」に、まさに“共感”したことが動機です。したがって、「コンサルティング」としての解説は、基本的に避けたいと考えています。
ただマイクロソフトが、現在、世界で最大の株式時価総額を誇るまでの企業(4月17日のコラムで紹介)になったのは、2019年に、サム・アルトマン氏率いる「オープンAI」に10億ドルの投資をし、その後も継続的に投資を行ってきたこと(累計で130億ドルと報道されています)が、大きく貢献しているわけで、劇的に進化し続ける「生成AI」について、語らないわけにはいかないと感じています。
ナデラCEOは「チャットGPT-2」後の世界を透視していた!
2019年の時点では、オープンAIの「チャットGPT」は、「2」の段階でした。同年2月に発表されています。マイクロソフトがオープンAIに最初の10億ドルを投資したのは、同年の7月ですから、「チャットGPT-2」の潜在力に注目したわけです。
この「チャットGPT-2」の実力が気になったので、「チャットGPT」に質問してみました。返って来た回答は…
GPT-2は、2019年2月14日に発表されました。このモデルは、その前身であるGPT-1と基本構造は同じですが、15億個のパラメータと40GBの学習データを持つことで、より高度な自然言語処理能力を実現しています。GPT-2の発表は、AI分野における言語モデルの進化と、生成能力の向上に大きなマイルストーンとなりました。
俄然興味が湧いてきたので、さらに「チャットGPT-2以降、チャットGPT-4oまでの発表タイミングについて教えてください」と質問しています。
GPT-3: 2020年6月に発表されました。これは、大規模な言語予測モデルとして注目を集め、自然言語処理における新たな基準を確立しました。
GPT-3.5: 具体的な発表日は公開されていませんが、GPT-3の後継モデルとして、2021年前後のデータを学習しているとされています。
GPT-4: 2022年11月に発表され2022年1月までのデータを基に訓練されています。
GPT-4o (Omni): 2024年5月に発表されました。このモデルは、以前のモデルよりも回答精度が向上し、人間のように感情豊かな音声会話も可能になるなど、大きな進化を遂げています。
これらのモデルは、それぞれの発表時にAIと自然言語処理の分野で大きな進歩を示し、多くの注目を集めました。特に最新のGPT-4oは、その高い性能と多様な機能で、AIの応用範囲を大きく広げています。チャットGPTシリーズの進化は、AI技術の急速な発展を象徴しており、今後もさらなる革新が期待されています。
「チャットGPT-4」に感動! さらに「GPT-4o」はミラクル!
チャットGPT-4の登場によって、2023年の世界の景色は様変わりしました。その「4」の説明が1行のみというもの面白いですね。というのも「4o(オムニ)」の進化が驚嘆すべきものであり、「チャットGPT」は、そちらを早く紹介したくなったからなのかもしれません(笑)
なお、「3.5」までは特に注目されていたわけではなかった…と解釈できそうです。昨年の12月13日に、『日経トレンディ』2023年版(2022年12月4日発行)と2024年版(2023年12月4日発行)を比較し、気づいたことをコラムにまとめています。
2023年版は2022年を総括する内容なのですが、そこには「生成AI」という表現は登場しません。ところが2024年版(2023年を総括)は、「生成AIに席巻された」と言ってもよいくらいの変わり様です。
両年の版とも「2030年大予測」をテーマとして掲げているにもかかわらず、「1年で予測が覆された」わけですから、識者と称される人たちの「大予測」も、「あてにならないなあ~」と感じた次第です。
そのあたりについては、架空のA課長に託して、少し“揶揄”を込めて、コメントしてみました(笑)
日経新聞は弁解しつつ、たった1年で予測を大幅に修正した!?
(A課長)
ありがとうございます。それでは、2024年1月号に転じましょう。サブタイトルは「生成AIが全てを加速させる。知らなきゃ生き残れない!」です。びっくりマークまで付して「煽って」います(笑)
そして、わざわざ、「1年前に見た未来が大きく様変わり~生成AIで“分化”した新しい5年後」と、弁解めいたコメントが続きます。
2024年版は、「未来予測キーワード」として35をピックアップしています。……
「チャットGPT-4」を実際に使ってみたとき、「おおっ!」と、思わず感嘆の声を漏らしてしまいました。ところが「チャットGPT -4o(オムニ)」のデモをYouTubeで視聴した際は、それどころではない「強烈なインパクト」を覚えています。
私たちが展開している「コーチング」は、そもそも「人と人との対話」によって成立します。「生成AI」がどんなに進化したとしても、それはあくまでも「機械」であり、「AGI」が輪郭を帯びてくるのは、まだまだ先のことだろう…と、思っていましたから。
AGIとは「Artificial General Intelligence」のことで、「人工汎用知能」と訳されます。内容については、「AGI(汎用人工知能)とは? 従来のAIやASIとの違いも解説」のタイトルでアップされている「SoftBank」のサイトにリンクを張っておきますので、ご覧いただければと思います。
『サラと気難しい人間たち』で「AGI」の未来を考えてみる!
AGIについて想像を膨らませているうちに、ロボットの「サラ」がイメージされてきました。「日本経済新聞×津村記久子<コラボ企画>『サラと気難しい人間たち』」をコラムで取り上げた3月27日の際には、「サラは“疑いなく”空想科学小説の出来事だ…」との認識でした。
ところが、「チャットGPT-4o」のデモを、YouTubeでさまざま視ているうちに、「サラ」のようなロボットが、“近いうち”に誕生するかもしれない…という思いに変わっています。
そのコラムで、<コラボ企画のあらすじ(日経新聞)>を引用しています。再掲します。
『サラと気難しい人間たち』<あらすじ>
物語の主人公・としみの仕事はオンラインで「上質な雑談」を提供するトークアテンダント。顧客は電子マネーの高額利用者だ。としみと暮らすAIロボットのサラは、アテンダントの肩代わりできるほど会話に長けている。しかしなぜか顧客たちは、生身の人間との雑談を求めるのだった。
作家の津村記久子さんは、掲載して2か月を経ずして「チャットGPT-4o」が発表されることを予測して、物語を組み立てた訳ではないと思いますが、「AGI」が実際に実現したら…とリアルに感じさせる見事なストーリーテリングです。
生身の人間とのコミュニケーションはどうなる…?
今回のコラムは、「コーチング」というより「コンサルティング」をまぶした内容になりました。最後に、「AGIは限りなく完成形に近づいているのかもしれない…」と予感を覚えた「オープンAI」のデモ動画を紹介します。
YouTubeに、さまざまアップされているのですが、日本語訳付で編集(15分程度)されたサイトにリンクを張っておきます。
ちなみに、『サラと気難しい人間たち』を創作した津村記久子さんは、「どんなにロボットが人間のようになったとしても、生身の人間とのコミュニケーションを求め続ける」という人間たちの未来を描いています。
坂本 樹志 (日向 薫)
現在受付中の説明会・セミナー情報
- 新入社員コミュニケーション1日研修 ─コーチングのスキルで学ぶ 報連相力アップ─
- 縦割り組織に悩む経営者・組織開発、人事担当者の皆様へ!「グループコーチングWA」体験会のご案内
- 【開催無料・中小企業経営者限定】できる経営者が選ぶ“壁打ち” エグゼクティブコーチング解説セミナー
- 人生が輝きだす最強のコミュニケーション術 無料講座
- 超入門初級コーチングいろは1DAY(10:00-17:00)セミナー
- ビジネスリーダーのための傾聴1DAYセミナー
- 1on1がうまくいかない・・なんとかしたいと思っているあなたへ上司として自信を取り戻す1on1スキル向上セミナー
- 【2026年1月、2月】コーチング経営アカデミー コーチ養成講座説明会
- 【無料開催・経営者・人事担当者限定】これで会社を変える!社員の自律と成長を促すコーチング活用セミナー