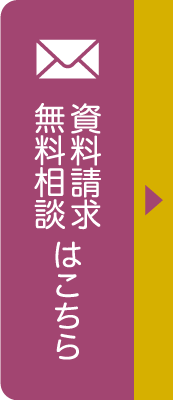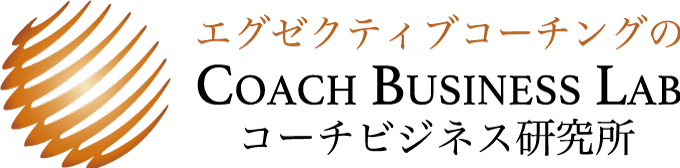それぞれの人の属性や過去の行動、選択反応の履歴データから人それぞれの好みを推定する。さらにその人の好みを代弁してくれるAI代理人をつくってもいい。データベースから推定されたそれぞれの人ならではの好みに基づいて。その人の好みに合った商品やサービスの配分を直接計算し推薦する。無数のデータ源から意思決定や資源配分の計算を行うのは自動化・機械化された市場経済アルゴリズムである。
(『22世紀の資本主義 やがてお金は絶滅する/成田悠輔』より引用)
生成AI(優等生)のアドバイスは手取り足取り…すぎると思う
前回のコラムの最後で…
「……ということで、当該インタビューについて(生成AIのアドバイスを“少しだけ”取り入れて)、次回コラムにしてみようと思います」、とコメントしています。
「当該インタビュー」とは、毎日新聞4月13日6面「デモクラシーズ~戦後80年インタビュー編」に登場した、経済学者 成田悠輔さんへのインタビューです。インタビュアーの中島昭浩記者が、「新著『22世紀の資本主義 やがてお金は絶滅する』が出版されました」と、最後に成田さんに訊ねているので、同書を再読し(2月に購入済み)、その中の179ページにある箇所を、引用してみました。
成田さんは、この「自動化・機械化された市場経済アルゴリズム」を「招き猫アルゴリズム」と命名します。成田さんが訴えたい「22世紀の資本主義」は、諸悪の根源たるお金を「いかに経済から抜くか」を考えた抜いた結果、その先に到来する(だろう)近未来社会のイメージです。成田さんは、「招き猫アルゴリズム」によって、その理想社会は訪れると、説きます。
「招き猫アルゴリズム」とは?
分権的で自主的な市場経済 vs. 集権的で意識的なメカニズムという二項対立は時代遅れになる。ゆっくりと、しかし着実に偏在するデータベースとアルゴリズムたちの群れが両者を乗り越えて統合する。
そしてお金の姿がない。値段や収入が見えない。これが招き猫アルゴリズムで起きるもう一つの大事な変化である。招き猫アルゴリズム経済では資源配分や意思決定がデータから直接に決まる。誰かが誰かに一宿一飯を与えるかもしれないし、逆に誰かが誰かを密着取材してドキュメンタリー化するかもしれない。そこにお金や価格のようなわかりやすく図れる物差しはなくてもいい。ただ何かを制作したり労働したり親切したり交換したりする「やりとり」が起きるだけ、あるいは推薦され誘発されるだけだ。(183ページ)
クレジットカードやモバイル決済などのキャッシュレス決済がかなり進展していますが、この場合「レス」といいながらも、裏付けは「銀行預金」という「お金」です。成田さんのイメージは、この「銀行預金のお金」も存在しない社会です。
「そんな社会は想像できない…」というのが、私たちの「感じ方」だと思います。成田さんは、その「お金」に替わるものを「アートークン」と名付け、次のように説明します。
やりとりはただの一方的な贈与を超えた双方向の行為である。それを可能にする仕掛けとして、招き猫アルゴリズムが食べて作るデータから唯一無二の証が発行される。やりとりを証明するこのかけらを「アートークン」と呼ぼう。アートのようにそれっきりの一つのもので、取り替えがきかず、複製できず、反復できない一回性と単独性を身に纏う。しかしトークンやお金のように経済取引を媒介する。アート+トークンだ。アートークンは量産できないばかりか、数えられず、比べられない。アートークンの身元保証と行先管理はブロックチェーンで分散実行する。(186ページ)
成田さんは、この「アートークン」を登場させる前に、NFTなどの解説についてかなりの字数を割いています。66ページから始まります。
NFTのユーティリティは進化し続けているが……
「代替できないトークン」(Non-Fungible Token)の爆発を思い出そう。2021年頃の喧騒を覚えているかもしれない。表面的なニュースのレベルでは、Twitter創業者ジャック・ドーシーの2006年の初ツィートが3億円で売れ、とこにでも猿のイラストにしか見えない「アート」に六本木のタワマン以上の値がつき、アーティストBeepleのデジタルアートのNFTが75億円で売れた。(66ページ)
私も、「その頃」を思い出しています。それもあって、2022年の6月にコラム(架空の対話)にしています。一読いただくと幸甚です。
新書240ページの同書は、第0章「泥だんごの思い出」、第1章「暴走」、第2章「抗争」、第3章「構想」と、刺激的なタイトルが付されています。韻を踏んでいますね。
成田さんは、第0章に入る前に、成田さんらしく(?)「はじめに開き直っておきたいこと」という見出しで、次のように「開き直り」ます(笑)。
いきなり言い訳をしておく、この本は経済(学)の解説書ではない。「経済学者が経済について専門知でわかっていることを広くわかりやすく伝える本」ではない。逆だ。むしろ「何かあやふやでよくわからない素朴な疑問をみんなで考える本」である。どんな学問でも、わかっているよりよく分からないことの方が圧倒的に多い。たまにはわからないことを気ままに議論してみるのもいいだろう。「プロ」も「素人」も一緒にだ。こういう精神で行こう。(中略)
この本では、プロの経済学者の末席を汚している私が、資本主義の未来像について、フワフワした想像をしてみたい。(27ページ)
私は、「いきなり」響きました。ワクワクしました。つまり成田さんは「リベラルアーツ」を語ろうとしている。成田さんは学者ですが、「アカデミズムで規定される論文作成の枠組みを放棄する」という宣言として、受けとめました。俗にいう「一般向けの本を書きますよ」とも解釈できますが、同書は99カ所の「※」を本文に付し「引用による根拠等」も示します。「一般向け」ともいい難い、難解な本です(笑)。
成田さんは、「学者」であることに飽きているのかもしれない…
「SF(Science Fiction)」は非現実であることを許された「未来」を描きますが、生成AIが劇的に進化している「現実」を実感すると、成田さんの描く「未来」は、「ひょっとして到来するかもしれない…」というリアリティーを、感じることができるのですね。ですから「SRF(Science Reality Fiction)」という、新分野の本として、私は受けとめています。
ところで、私は前回のコラムで、「成田さんの発言は過激であり、物議を醸している」、とコメントしています。ただし、「実際の語り口は冷静沈着そのもので、感情の高ぶりを一切相手に感じさせないスタイルです」と、意図的な自己プロデュース力によって「成田スタイル」をつくり上げている…このように造型しました。バランスです。同書も、第1章「暴走」第2章「抗争」のタイトルが示すように、過激な発言が散りばめられています。「CBLコーチング情報局~コーチング大百科」で、このところ、『ブッダの夢』を引用し「悪の倫理」についても書いていますから、「成田さんの悪」が感じられるコメントについても、思考してみようと思います。
・お金は人間の恥部である。(12ページ)
・ダメだ。そんな煽り気味の資本主義礼賛で終わっていいはずがない。逆襲はここからだ。心身も物事も人格もすべてがデータになるにつれ、市場経済の心臓に異常が起こる。お金だ。(19ページ)
・こうして、古き良き物理国家を新種の情報国家が駆逐していく。市場と国家の抗争が今世紀の基調低音になる。(21ページ)
・すでに見た赤字企業の時価総額の爆発と似て、未来に向かって新しい経済的生態系を作り出してくれそうな何か巨大な価格がついたり剝れたりするようになった。そこにあるのは革命と詐欺のマリアージュである。(56ページ)
・資本主義経済はやたら口がうまい営業や占い師みたいなものだ。ここまで触れてきた新しそうに見える事実群もそうである。(58ページ)
・だからこの本では、変幻自在に中身を変化させながら有象無象の有形無形な未開拓領域を商品にし稼いでいく運動をざっくり「資本主義」と呼ぶ。(59ページ)
・あらためて資本主義とは何か? 定義はない。定義できない変態性が資本主義だ。資本は常に未開拓領域を食べ、価格と利益を排泄し、中身を変化させながら肥える。その変化と増殖こそが資本主義の本質である。(66ページ)
成田さんの「熟慮」は、切れ味鋭い「決めつけ」として表れる
これくらいにしておきましょう。決して上品な表現ではありませんが、実にインパクトがあります。「決めつけ」ですが、膨大な知識を動員した「熟慮」によって、「自信」が形成され、切れ味鋭い(ロジックを纏った)「成田流話芸」に昇華しています。
今回のコラムは、『22世紀の資本主義』の「感想文」になってしまったようです。実は同書を念入りに再読したのは、目的がありました。
前回のコラムで、私が響いた成田さんの回答(毎日新聞インタビュー)は、「敵はむしろ民主主義の結果として達成してしまった豊かさであり、幸福。そんな仮説を持ち始めています」であると、記しています。この「成田さんの<思想>が感じられる文脈が、同書に存在するかもしれない」という期待です。一字一句を、目を皿のようにして追っていったのですね。結論は… 見つけることが出来ませんでした。
エッジの利いた<思想>の誕生を鶴首して待つことにします
なぜなのか? いろいろ思考してみました。理由は不明です。それでも私は、なんとなくわかるような気がしています。
この「仮説」は、成田さんの中で、まだ「仮説」に留まっているのでしょう。成田さんのことですから、あらたな思考を起動し、脳を高速回転させているのだと想像します。そして私は、エッジの利いたその<思想>が開示されるのを、鶴首して待とうと思います。
坂本 樹志 (日向 薫)
現在受付中の説明会・セミナー情報
- 新入社員コミュニケーション1日研修 ─コーチングのスキルで学ぶ 報連相力アップ─
- 縦割り組織に悩む経営者・組織開発、人事担当者の皆様へ!「グループコーチングWA」体験会のご案内
- 【開催無料・中小企業経営者限定】できる経営者が選ぶ“壁打ち” エグゼクティブコーチング解説セミナー
- 人生が輝きだす最強のコミュニケーション術 無料講座
- 超入門初級コーチングいろは1DAY(10:00-17:00)セミナー
- ビジネスリーダーのための傾聴1DAYセミナー
- 1on1がうまくいかない・・なんとかしたいと思っているあなたへ上司として自信を取り戻す1on1スキル向上セミナー
- 【2026年2月】コーチング経営アカデミー コーチ養成講座説明会
- 【無料開催・経営者・人事担当者限定】これで会社を変える!社員の自律と成長を促すコーチング活用セミナー