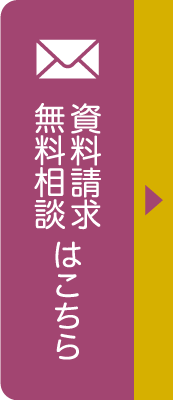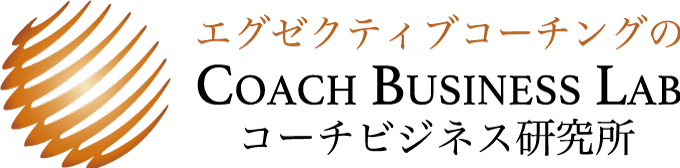モバイルが苦戦するなか、マイクロソフトは事業の多角化を進めた。14年に3代目のCEOに就任したサティア・ナデラ氏は「モバイルファースト」「クラウドファースト」を旗印に経営方針を大転換した。特にAI時代を予見し、オープンAIに接近。まだChatGPTが世に出ていない19年から同社にクラウドのインフラを提供し、見返りにAI技術の優先使用契約を得た。企業向けにITインフラとAIをセットで提供する戦略へカジを切った。
(日本経済新聞2025年3月29日7面「マイクロソフト栄枯盛衰の50年~AI・クラウドで復活」より引用)
日経新聞1面に「おやっ?」と感じた理由を語ってみます
3月28日(金)の早朝、日経新聞を「さて見るか…」と、1面をテーブルに広げたところ、「おやっ?」と感じる記事が目に入りました。「マイクロソフト、独自AI~CEO開発表明 チャットGPTを補完」という見出しで、サティア・ナデラCEOが27日に、「人工知能(AI)の基盤モデルを業務ソフト向けに自社開発することを明らかにした」ことが、取り上げられていたからです。19面には「関連記事」として、紙面のかなりのスペースを使い、その詳細が綴られています。
さて、私が感じた「おやっ?」なのですが、これほど世界的に有名なCEOですから、日経新聞の1面に登場したとしても「おやっ?」と感じることはないのでは…と思われるでしょう。その疑問を「私への嬉しい質問」と受けとめ、説明させていただきます。編集委員の奥平和行さんは19面の最後をつぎのように締めくくっています。
マイクロソフトなど米IT大手の成長を支えてきた自由貿易への逆風も強まるばかりだ。米IT業界では政権に露骨にすり寄る動きも目立つ。取材の最後、ナデラ氏に自社の方針と相容れない政策に対して経営者は口を閉ざすべきか声を上げるべきか尋ねるとこう答えた。「これまで守ってきた原則に忠実であり続けることに変わりはない」
(編集委員 奥平和行)
奥平さんは、この記事を明瞭な意図をもって書いています。メタのザッカーバーグCEO、グーグルのピチャイCEOなどIT業界トップが、トランプ大統領に「すり寄る動き」を見せている。ところが、ナデラCEOにはトランプ大統領への秋波は感じられない。トランプ大統領が誕生して以降、大きくメディアに登場することもない。「果してナデラ氏の本心はどこにあるのだろうか…」との思いが、日経新聞とテレビ東京との共同取材につながった、と理解しました。奥平さんのこの「想い」を、私はどうも共有していたようです。だから「おやっ?」と感じたわけですね。
ナデラCEOにはトランプ大統領への秋波は感じられない…
ナデラ氏の答えは「これまで守ってきた原則に忠実であり続けることに変わりはない」でした。トランプ政権下の米国で、こうきっぱり言葉にする(できる)ナデラCEOという存在に、力をいただきました。感動そのものです。
28日の「1面+19面」の翌日、29日「7面総合」に、「マイクロソフト栄枯盛衰の50年」というタイトルが付され、マイクロソフトの半世紀を振り返る特集が組まれます。冒頭は、その記事から引用しています。私は、ナデラ氏の自伝である『Hit Refresh~マイクロソフトの再興とテクノロジーの未来』を読み込み、感銘を受けたことで、ちょうど1年前に、10回ほどコラムを書く機会を得ました。したがって、50年のマイクロソフトの歴史は鮮明に記憶に留まっています。その初回のタイトルは、「今回より、マイクロソフトCEOサティア・ナデラ氏の『Hit Refresh』を紐解き、「共感の経営」についてコラムを綴ってみようと思います」です。
私はその書き出しを…「マイクロソフトは1975年に、ビル・ゲイツとポール・アレンによって創業されました。つまり、変化の激しいIT業界にあって、50年の歴史を有する老舗中の老舗です。」…と始めています。日経新聞の29日7面の書き出しも、ここから触れていますので、ちょっと嬉しくなりました(笑)。
1975年4月4日、マイクロソフトは米ハーバード大学の学生だったビル・ゲイツ氏と、友人のポール・アレン氏が設立した。社名は「マイクロコンピューター」と「ソフトウエア」を掛け合わせて命名した。
マイクロソフトの50年は、「栄盛」→「枯衰」→「大復活」!
日経新聞はタイトルに「栄枯盛衰」という4文字を使っています。「栄盛」は、次のように描かれます。
世界的なブームを巻き起こした「ウインドウズ95」は発売1年で4000万本以上を販売した。ウェブ閲覧ソフト(ブラウザー)「インターネットエクスプローラー(IE)」は無料でセット提供され、インターネットの一般家庭への普及を促した。
2000年代にはパソコンの9割をウインドウズが占め、パソコンの頭脳役には米インテルが最適化したCPU(中央演算装置)を搭載した。「ウインテル帝国」と呼ばれる一時代を築いた。
「盛者必衰は歴史の常道」とも指摘されますが、実際に「ウインテル帝国」の片翼の覇者「インテル」の現在は、かなり過酷な状況です。マイクロソフトについても「枯衰」の危機に見舞われます。
クリントン米政権下の1998年、司法省が中心となり反トラスト法(独占禁止法)違反の疑いでマイクロソフトを提訴した。セット販売が市場競争をゆがめ、競合の参入を阻んでいるというのが主眼にあった。
マイクロソフトは解体を免れたものの、世界を席巻したからこそ、このビジネスモデルにきしみが生じます。そうこうするうちに、IT業界に地図の塗り替えが始まるのです。グーグルの急成長、通販の会社であったアマゾンが「クラウド」によって、紛うことなくIT企業として、大変身を遂げるのです。
そのあたりについては、「AGI」は実現するのか? …サティア・ナデラCEOは2019年の「チャットGPT-2」に未来を予感し、2024年5月の「チャットGPT-4o」に結実した! のタイトルで、コラムにしています。私はナデラ氏を「内も外もコーチャブルそのままが歩いている人」と、造型しています。
ゲイツ氏は「マイクロソフトは終わった」と実感した…?
『Hit Refesh』には、日本の失われた30年と同時代の、米国(つまり世界)のIT業界の激動の歴史が、活写されています。アマゾンについて、ナデラ氏は次のように語っています。なつかしい響きの「クライアント/サーバー時代」から「クラウド」へのパラダイムチェンジが起こるのです。
アマゾンはいち早く、AWSでクラウドをビジネス化した。彼らは早い段階から、書籍や映画などの小売製品を販売するために自社で使用しているクラウド・インフラが、他社の業務にも役立つことを理解していた。そして、各社が自前でクラウドを構築するよりもはるかに安い価格で、そのインフラを少しずつ他社に貸し出せばいいことに気づいていた。2008年6月時点で、アマゾンには、クラウド・プラットフォーム向けにアプリケーションやサービスを構築するデベロッパーが18万人いた。一方マイクロソフトには、商業的に利用できるクラウド・プラットフォームがまだ存在していなかった。(70ページ)
そして「2008年」が到来します。ナデラ氏は、マイクロソフトの2008年を次のように描写しています。
こうした状況すべてが、マイクロソフトを苦しめた。2008年の大不況の前からすでに、株価は下降を始めていた。さらにその年には、かねての計画通り、ビル・ゲイツが「ビル&メリンダ・ゲイツ財団」の仕事に専念するためマイクロソフトを去った。(70ページ)
私は、この箇所で「ゲイツ氏は『マイクロソフトは終わった』と実感した…?」と見出しを付しています。
サティア・ナデラ氏は「共感の未来」を展望します!
ナデラ氏が3代目CEOに就任したのは2014年です。日経新聞28日の19面を引用します。
ビル・ゲイツ氏とスティーブ・バルマー氏に続き、14年に3代目のCEOに就任したナデラ氏はそれまで出遅れていたクラウドやスマートフォンなどのモバイル分野を優先する方針を掲げて成果を出した。株式時価総額は就任時の約3000億ドル(当時の為替レートで31兆円)から3兆ドル規模まで拡大した。
ここでは「クラウドやモバイル分野を優先する戦略をとったから成果を出せた」と、シンプルに書かれていますが、どん底ともいえるマイクロソフトを大復活させた「真の理由」は、トップであるナデラ氏の人格であり、哲学であり、器の大きさであったことが、『Hit Refresh』を読むことで伝わってくるのです。同書は2017年の刊行ですから、復活劇は顕在化していません。それでも同書には、現在のマイクロソフトに至る「未来」が予感されるのです。
今回のコラムは、『Hit Refresh』の「あとがき」にある、ナデラ氏の最後のメッセージ(最終ページです)を引用して終えることにします。トランプ大統領とは、全く違う世界をナデラ氏は展望しています。
こうした文化は、私たちが社外でもつくり出したいと考えている世界、すなわち、つくり手がすばらしいことを成し遂げられる世界の縮図でなくてはならない。だが、同じくらい大切なのは、それが同時に、すべての人が最高の自分になれるような世界、肌の色や性、宗教、性的指向の多様性が理解され、祝福されるような世界でもあることだ。私は、同僚が共感から生まれた卓抜な意見を言うのを聞いたり、会社を自分の情熱や創造力のためのプラットフォームとして活用した人によって製品のブレークスルーが起きたりした時に、マイクロソフトは正しい方向に進んでいると実感する。
「ヒット・リフレッシュ」とはどういう意味か。その答えは読者自身で見つけてほしいと思う。まず、自分の組織やコミュニティーで周りの人と話し合ってみることから始めてほしい。そして、あなたが学んだことをぜひ私に教えてほしい。私も、同じように学んでいくつもりだ。
坂本 樹志 (日向 薫)
現在受付中の説明会・セミナー情報
- 新入社員コミュニケーション1日研修 ─コーチングのスキルで学ぶ 報連相力アップ─
- 縦割り組織に悩む経営者・組織開発、人事担当者の皆様へ!「グループコーチングWA」体験会のご案内
- 【開催無料・中小企業経営者限定】できる経営者が選ぶ“壁打ち” エグゼクティブコーチング解説セミナー
- 人生が輝きだす最強のコミュニケーション術 無料講座
- 超入門初級コーチングいろは1DAY(10:00-17:00)セミナー
- ビジネスリーダーのための傾聴1DAYセミナー
- 1on1がうまくいかない・・なんとかしたいと思っているあなたへ上司として自信を取り戻す1on1スキル向上セミナー
- 【2026年1月、2月】コーチング経営アカデミー コーチ養成講座説明会
- 【無料開催・経営者・人事担当者限定】これで会社を変える!社員の自律と成長を促すコーチング活用セミナー