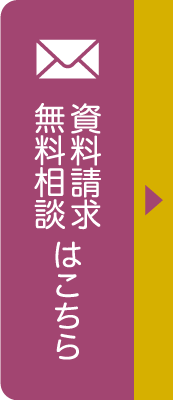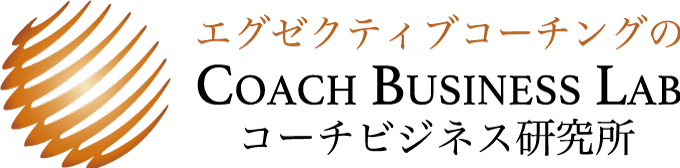NASAでもいじめには遭いませんでした。大人になっても、父が選んでくれたモスグリーンのランドセルを背負った経験が生きてくるんです。小学生のときと同じで「みんながもっていないものは何か」を一生懸命考えました。子供時代、ランドセルは赤と黒がマジョリティーでした。だけど、「緑のランドセルはこれしかないんだよ」って言ってあげると、私をからかっていたはずの子たちが、逆に欲しがるようになったわけです。だから、私はマイノリティーを盾にとりました。
(毎日新聞2025年3月18日11面・教育「東京理科大学特任副学長・向井千秋さんインタビュー」より引用)
3月18日(火)に大宮に用向きがあって出かけ、いつもの町中華で昼食を摂る際の「ながら新聞」を求め、南銀口階段下のKIOSKで毎日新聞を買っています。その11面は、田原総一朗さんによる向井千秋さんへのインタビューです。私は、そのタイトルに引き付けられました。
五感を磨き深い学びを!
前回のコラムは「未来」がテーマです。これまで、この「未来たち」をたくさんコラムで書いてきた自覚もあり、サイト内検索窓に「未来」と入力すると、104のコラムがヒットしています。(株)コーチビジネス研究所は、このホームページとは別に「CBLコーチング情報局~コーチング大百科」を「infoサイト」として公開していますので、今回はこちらのサイト内検索窓に「五感」を入力してみました。すると…28ほどが該当しています。

コーチングとは「対話」です。その「対話の本質」は、単純な「言葉」のやりとりだけではない「五感」の交換です。クライアントとコーチの間に、この「五感の交流」が生まれた時、コーチングは息づいてきます。
田原総一朗さんの最初の質問と向井千秋さんの回答を、まず引用します。
(田原)
人生でやりたいことを、見つけてあげることが教育だと思うのですが。
(向井)
そう思います。私が東京理科大でやっている宇宙教育では、学生に「何を勉強したいのか、何をやりたいかを教えてください。いくらでも先生はいます」と伝えています。
そして幼いころから、五感をもっと働かせ、感覚を研ぎ澄ませるような教育をしてほしいです。私は医者なので患者さんを診察する時は、必ず自分の目で見て感じるようにしていました。看護師さんから届くデータや伝聞では分からないことがあるからです。群馬県の田舎で育ったので、四季折々の違いなどを肌で感じてきたことも影響しているのかもしれません。
「五感」をもっと働かせ、感覚を研ぎ澄ませる教育をしてほしい!
コーチングだけでなく、人とかかわりを持ち、支援そのものが仕事となっている職業はさまざま存在します。その嚆矢が「医者」であるといっても過言はないでしょう。そして、私たちが抱くその職業イメージは、「医学分野という最先端の科学的知識を保有する専門家」です。そこには「情報の非対称性」が存在しますから、対等ではない関係性を受け入れてしまうようにも感じます。医者は「先生」であり、私たちは「患者」です。「クライアント」ではありません。「対話」はなかなか生まれにくい…
科学の進歩とは「あいまい性」を除去していくプロセスです。特に医学における「診断技術」の進歩は、目覚ましいものがあります。その結果、医者は患者と一切言葉を交わさないで、診断を下すことも、理論的には可能です(病態によりますが)。実際にそのようにやっている「お医者さん」も、多いように感じます。
一方で、科学とは既存の理論・技術が覆されることで、新たな最先端が発見されるプロセスです。「圧倒的な未知の世界」こそ、リアルですよね。向井さんは、慶応義塾大学医学部卒の「医学博士」ですが、その向井さんが「五感」を深く語っている。
理科教育もそうですが、教科書であっても、まずは研ぎ澄ました自分の五感を頼りにしながら「本当かなあ」と疑ってみた方が深い学びになります。教科書だって時代が変わったり、定説が変わったりすれば。書かれる内容も変わるのです。
日本の大学は、研究力が下がったとも指摘されます。その一因は「出口政策」になっているからです。政府からは「要するに、この研究は何に役に立つのですか」といったことが言われがちです。でも、本来、研究というのは「すごい」「不思議だ」「面白いな」と思えることを、どこまで探求できるかではないでしょうか。
向井さんは、東京理科大学の副学長ですから、「大学教育」に言及しています。この、毎日新聞3月18日(火)の記事を読んだ時「コラムにしてみようかな…」とは思ったのですが、その際はPCのキーを打っていません。ところが、日本経済新聞3月23日の日曜版1面「チャートは語る~分厚い教科書 理想の手探り」というタイトルの記事に目を通したとき、向井さんの「想い」と、私の「書こう」という動機が結節しました。この記事の「20年でページで3倍 知識×思考力の両立途上」という見出しが示唆するように、「主体的な学びを促したい」という教育の目的(理想?)と、教育現場のギャップが、どんどん広がっている現実が指摘されるのです。
学習範囲が広くなるとともに、近年は考えを手助けするヒント付きの解説や、ケーススタディーのような発展的な問題が盛り込まれ、厚みが増した。20年度の学習指導要領で「主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング、3面きょうのことば)」が導入され、さらに流れは強まっている。
理想と現実のギャップは、さまざまなところで見受けられます。日本の未来を占う最も重要な分野である「初等教育」において、このキャップが「極端な矛盾」として現出しているのではないでしょうか。
「初等教育」の現場に「極端な矛盾」が押し込められている…
文科省の24年度調査では、年間の標準授業時数を超える公立学校は小学5年で89%、中学2年で84%に上る。
比例して教員が授業準備に要する時間は長くなる。人手不足に加え、増え続ける不登校の子供の対応など授業外の業務負担も重なる。
この背景も相まって、「大事な部分を取捨選択せず網羅的に教えようとする教員が少なくない」と指摘する桐蔭大学の溝上慎一理事長(教育学)のコメントが取り上げられています。「網羅的に教えようとする教員」は、どのように想像しても「五感」を発揮し、授業をしているようには感じられませんよね。
「CBLコーチング情報局~コーチング大百科」に、河合隼雄さんが、ある小学校の授業を参観した際の、「あるある」が伝わってくるシーンが描かれています。(「コーチングの時代」が今まさに到来している!)。
一例をあげる。「ばら」という詩についての国語の授業で、教師は、バラの美しさについて生徒の鑑賞力を高めようと、バラについて生徒に思いつくことを何でも言ってみなさい、という。美しい花だとか、誕生日に貰って嬉しかった、などという発言のなかで、ある生徒が「トゲがある」と言った。バラの美しさについて焦点を当てている教師は、一瞬不愉快な顔になった。すると、クラスの生徒たちはそれを感じとってしまって、「トゲ」の発言をした生徒に冷やかな視線を向ける、ということがあった。
子どもたちは先生の気持ちを察する能力が高いので、一見、生徒たちが活躍している授業に見えながら、先生の意図した流れにそのまま乗っかっているような授業になることが多くないか、を反省する必要がある。子どもたちは自分のなかから湧き出てくるものによるのではなく、先生の意図をできるだけうまく、早くキャッチして反応しようとするだろう。これで「個性を磨く」教育ができるだろうか。いわゆる「優等生」は創造性が著しく少ない、などということになってしまうのである。
「気配を共有する能力」は「同調圧力」と表裏一体
日本では、生徒の「察する能力」はこうやって「教育」されていくのだな…と感じてしまいます。言語化し難い「気配を共有する能力」は、日本文化の美点です。ただし、何ごとも表裏があるように、それが「同調圧力」という「見えない空気」を受容してしまう多くの日本人をつくっているのかもしれません。
毎日新聞は、向井さんの次の言葉を最後の〆として掲載しました。引用します。
(向井)
小さなことを何度もやっているうちに成功体験になります。ユニークな自分がチームの役に立てれば、みんなも喜ぶし、自分もうれしい。それが、どんどん大きくなるうちに同調圧力に負けなくなります。
ユニークさを持った人たちが集まれば、強いチームができる。それがダイバーシティーです。スペースシャトルでミッションをこなした、私たち宇宙飛行士もそんなチームでした。
今回のコラムは、毎日新聞と日経新聞を取り上げました。最初と最後の両方を毎日新聞にしてしまうと、バランスを欠いているようにも感じるので(笑)、最後は日経新聞の主張を引用することにします。前回のコラムと同様、「未来」につながっています。
未来への可能性を引き出す「授業のあり方」を探求したい!
膨らんだ教科書の中には、探求の方法を手取り足取り詳述するような内容も散見される。木村氏(ベネッセ教育総合研究所 主席研究員)は「教えすぎは子どもの成長の機会を奪い、自ら思考して乗り越えることにつながらない」と語る。未来への可能性を引き出すためにも授業のあり方を見つめ直す時に来ている。
坂本 樹志 (日向 薫)
現在受付中の説明会・セミナー情報
- 新入社員コミュニケーション1日研修 ─コーチングのスキルで学ぶ 報連相力アップ─
- 縦割り組織に悩む経営者・組織開発、人事担当者の皆様へ!「グループコーチングWA」体験会のご案内
- 【開催無料・中小企業経営者限定】できる経営者が選ぶ“壁打ち” エグゼクティブコーチング解説セミナー
- 人生が輝きだす最強のコミュニケーション術 無料講座
- 超入門初級コーチングいろは1DAY(10:00-17:00)セミナー
- ビジネスリーダーのための傾聴1DAYセミナー
- 1on1がうまくいかない・・なんとかしたいと思っているあなたへ上司として自信を取り戻す1on1スキル向上セミナー
- 【2026年1月、2月】コーチング経営アカデミー コーチ養成講座説明会
- 【無料開催・経営者・人事担当者限定】これで会社を変える!社員の自律と成長を促すコーチング活用セミナー