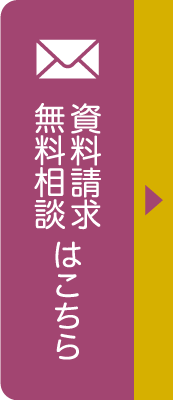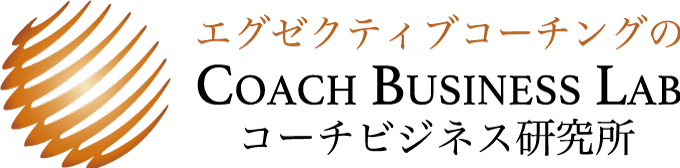(中山)
「ドラえもん」という漫画が日本にある。一種のAIだが、神でも恐れられる対象でもなく、友達かペットだ。日本人は脅威というより少し引いた目線でAIを受け入れるかもしれない。
(ハラリ)
「面白い議論だし、ドラえもんも読んでみよう。いつかそんな議論もできたらいい」
(日本経済新聞2025年4月6日2面「『直言』AIを民主主義の味方に~ユヴァル・ノア・ハラリ 歴史学者」より引用)
「ドラえもん」は日本が生み出した普遍化できる思想かもしれない
世界が大混乱です。4月6日の日曜版の日経新聞1面は「関税応酬 世界の市場動揺」の大きな文字が踊っています。見出しは2つ、「NY株2231ドル安 下げ幅史上3位」「米国債 利回り一時4%割れ」と、トランプ米政権の相互関税と中国の報復関税が大きくアナウンスされたことで、「大不況に身構える心理」が世界に広がっています。
このタイミングで、何をテーマにコーチングコラムを書けばいいのか… とても悩みます。そして、2面を開きました。日曜版の2面は、日本・世界の識者にインタビューする『直言』です。今週は、「サピエンス全史」「ホモ・デウス」の世界的ベストセラー作家であり歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリ氏でした。
日経新聞が、この『直言』をスタートさせたのは、2023年6月18日です。トップバッターは、「沖縄科学技術大学院大学(OIST)」のカリン・マルキデス学長でした。OISTについては「認知ゼロ」だったこともあり、かえって興味を覚え、真剣に読んでみました。そして「沖縄にすごい大学院大学があった!」ことを知ります。このことがきっかけで、毎週日曜日の2面『直言』を取り上げてのコーチングコラムを、一年ほど続けています。2024年3月20日には、それまでの『直言』を振り返ってみました。
『直言』はインタビューですが、質問者である日経新聞の記者は、ジャーナリストの気概を持って「対話」で臨みます。ですから、コーチングを感じることができるのです。日経新聞は現在も『直言』インタビューを続けていますから、私も伴走している気持ちです(笑)。
前置きはこのくらいにして…
『直言』インタビューはコーチングの「対話」に通じる
全体を通しての印象は、「ハラリ氏はAIに対して、とてもネガティブだなあ…」でした。質問は全部で12ほど。一つの質問に対し、1つ~4つの「 」で、ハラリ氏の回答を掲載します。引用は最後の質問と回答です。「ドラえもん」が登場する背景を、インタビューを終えた中山淳史本社コメンテーターは、次のように語っています(インタビューから)。
都内ホテルの最上階。片付けをして部屋の外に出ると、ソファで「ドラえもん」を読むハラリ氏の姿があった。筆者が取材中に贈った英語版だった。
サービス精神だった可能性もある。だが、まだ49歳の若き知の巨人は人類を考察するのに日本の漫画とも向き合うのだと感心した。
主張していたのは「信頼」の重要性だった。人間が信じあうことは民主主義の根本であり、AIやアルゴリズムに負けない社会をつくる力になる。だから、「普遍的価値観」を壊すトランプ氏、あるいは壊しかねないAIには手厳しい。……
中山さんも「手厳しい」とコメントしているように、AIに対する見方は、ハラリ氏の「価値観」が濃厚に現れているように感じます。5番目の質問で、中山さんは「AIを、民主主義を強くする道具にできることも信じたい」と、ハラリ氏からポジティブな見解を引き出そうとしますが…
ハラリ氏は、『偽物人間』を法的に規制すべし! と訴えている
「民主主義を守る方法は2つある。まずボット、つまりインターネット上で人間のように振る舞う『偽物人間』を法的に禁じることだ。人と区別ができない状態では、偽の物語を流して誤った方向に人を導く。人間もそれに気づかない」
「もう一つは開発主体の企業がAIの行動に責任を負うことだ。IT(情報技術)企業は『言論の自由だ』などと主張するが、彼らの言論はAIのアルゴリズムに人間のふりをさせ、何かを決めさせているだけだ」
「要は、IT企業のビジネスモデルに原因はある。彼らは人々に長い時間、AIサービスを使わせたい。エンゲージメントを高めたい。それがフェイクニュースや陰謀論、憎しみをまき散らす元凶になっている」
「我々は人類史上最も洗練された情報技術を持つが、まともに話すことも意見の一致を見ることもしなくなりつつある。米国の民主党も共和党ももう、何かで合意することはないのではないか」
いかがでしょうか? 悲観論そのものです。最後の「合意することはないのではないか」は、「文脈全体を総括」するかのようですね。
ハラリ氏の新著『NEXUS情報の人類史』を読んでいる中山さんの、11番目の質問に私は響きました。冒頭の「ドラえもん」が登場する最後の質問の一つ前です。
中山さんは、ハラリ氏の思考様式の本質を引き出した
(中山)
本を読んでいて率直に感じたのはユダヤ教やキリスト教という一神教の視点で書かれている点だ。仏教も神道も受け入れる日本人はAIの恐れ方が違う気もする。
(ハラリ)
「視点がそうなのは間違いない。2つの宗教の興味深いところは聖典に基づいている点だ。神聖なのは自然でも人間でもなく、聖典だ。聖職者の権威は聖典に書かれていることを記憶し、解釈することで生まれる。だが、AIは人間より多くのことを記憶し、解釈することで生まれる。だが、AIは人間より多くのことを記憶し、解釈できる可能性がある。それゆえにAIという存在により強く恐れを抱くのかもしれない。権威の移行が起きかねない」
(株)コーチビジネス研究所は、ホームページとは別に、「Infoサイト」で、「CBLコーチング情報局~コーチング大百科」を公開しています。4月7日(月)は、スピノザの「神即自然」を紹介しています。ハラリ氏は、それとは異なるスタンスのようですね。
さまざまの識者の見解を引用しつつ、「コーチングはリベラルアーツ」であることを、書き続けているのですが、河合隼雄さんの思想に共感を覚え、コーチングに敷衍しています。
私が今回の『直言』で嬉しかったのは、中山さんも河合隼雄さんを紹介しているのですね。「インタビュアーから」にある、中山さんのコメントの最後です。
河合隼雄さんの「包括的な視点」は魅力的です!
日本にも情報、宗教、会社と信頼を関連づけた評論や経営書は多いと告げると興味深そうに聞いていた姿が印象的だった。梅棹忠夫、河合隼雄、岩井克人。ハラリ氏もいずれ手に取りそうな気がしたが、そうした好奇心こそ人間がAIに負けない一歩なのだろう。(本社コメンテーター 中山淳史)
そこで、生成AIにハラリ氏と河合隼雄さんの「思想」の違いを質問してみました。回答を引用します。
(Copilotの回答)
ハラリ氏の宗教に関しては、彼はイスラエル出身のユダヤ人家庭に育ったとされていますが、彼自身は世俗的であり、宗教的な実践者というよりも哲学的な視点から宗教や歴史について考察している学者だと言えます。彼の仕事は、一神教的な視点と彼自身の個人的なスタンスを使って、現代の問題やテクノロジーの進化に伴う影響を分析しています。
対して、河合隼雄さんの思想は「二分法を超える日本的な仏教観」と「異なる価値観を結びつける柔軟さ」を特徴とし、人間や社会に対する深い理解と包括的な視点が魅力的です。おっしゃる通り、ハラリ氏が一神教的な枠組みからAIを懸念するのに対し、河合隼雄さんの思想はそれを超えた、人間そのものの本質的な価値や可能性を捉えようとするものであり、これが二人の大きな視点の違いとも言えます。
二人の思想を比較し、それぞれの価値を見出すことは、AI時代における人間の役割や存在意義を問い直す際に非常に意義深い視点を提供してくれます。
コーチングはリベラルアーツです。「分断」「混沌」が世界を席巻しつつある状況だからこそ「コーチングの出番が到来している」、と受けとめ、これからもコーチングを語り続けていこうと思います。
坂本 樹志 (日向 薫)
現在受付中の説明会・セミナー情報
- 新入社員コミュニケーション1日研修 ─コーチングのスキルで学ぶ 報連相力アップ─
- 縦割り組織に悩む経営者・組織開発、人事担当者の皆様へ!「グループコーチングWA」体験会のご案内
- 【開催無料・中小企業経営者限定】できる経営者が選ぶ“壁打ち” エグゼクティブコーチング解説セミナー
- 人生が輝きだす最強のコミュニケーション術 無料講座
- 超入門初級コーチングいろは1DAY(10:00-17:00)セミナー
- ビジネスリーダーのための傾聴1DAYセミナー
- 1on1がうまくいかない・・なんとかしたいと思っているあなたへ上司として自信を取り戻す1on1スキル向上セミナー
- 【2026年1月、2月】コーチング経営アカデミー コーチ養成講座説明会
- 【無料開催・経営者・人事担当者限定】これで会社を変える!社員の自律と成長を促すコーチング活用セミナー