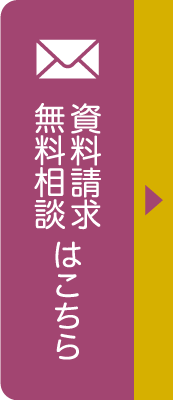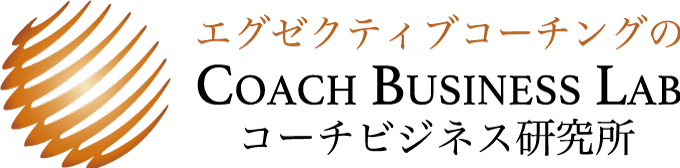今、米中の貿易戦争が問題になっています。
今回も友人Hさんとの対話からです。
「戦争とは相手を我々の意志に従わせるための暴力行為である。クラウゼビィッツが戦争論で定義づけていますが、シンプルな表現なのでしっかり覚えました。暴力までいってしまうとさすがに…なので代替手段としての関税合戦ですね。妥協の拒否です」
「国と国、という壮大なレベルではなく、人と人の関係をこの定義を使って考えたとき、自分と相手がいて、自分の意志と相手の意志が異なっている。自分の意志を押し通したい。でも相手は受け入れず拒絶する。双方の意志を何とか近づけ妥協点が見いだせればコトは解決するのだけど、双方が意志を曲げない」
「人間関係がスムーズにいかない、という状況の説明にぴったりだと思います」
Hさんは戦争論から人間関係の軋轢を解説します。その中で「妥協」という言葉が登場していますが、「妥協」について考えてみましょう。
「相手の意志の本質は何なのか?」
相手の立場になって想像力を働かせてみましょう。
そこまで真剣に私に訴える、ということは、それを訴えなければならない理由があるはずだ。でもその理由を言うことは、自分のプライドが許さない、自分の弱みを見せることになる…など、水面下に何かがあるのかもしれません。
絶対言ってほしくない言葉、触れてほしくないコト、つまり「琴線」、誰にでもありますね。
その「琴線」を守るために必死になったりします。
このような思考のプロセスを経てみると相手に対する感覚が違ってきます。
つまり少し余裕が生まれ、相手に対して優しく接することができそうです…
さてHさんです。中国の「琴線」…国家体制の「根幹」について語りが始まりました。
「1949年に毛沢東が天安門の壇上に立ち中華人民共和国の建国を宣言しました。100年という期間、どのような人物、組織も成し遂げることができなかった奇跡を実現したのは共産党であり、共産党そのものが国家である、という勝利宣言です」
「改革開放政策を正当化するために社会主義市場経済という言葉を生み出し、あくまでも共産党が指導する、という国家体制です。つまり“根幹”ですね」
「米国はこの“根幹”に迫っています。中国の国有企業の役割・中核的産業政策を見直せ!という要求なので、さすがに習近平は妥協のしようがない、折り合えない、ということだと思います・・・」
この後、Hさんは米国の立場を語り始めますが、それは次回としましょう。
米中貿易摩擦のような国家間の問題については、そんなに簡単ではないでしょうが・・・、
会社と個人の価値観など「価値観の調和」を考えることはとても重要です。
私たちは、時として多くのものに妥協しながら生活しています。その多くは不必要なものであり、私たちを立ち止まらせ、苦しみを与え、時間とエネルギーを消耗させます。
「妥協」することで成長の妨げになっていないだろうか?
「妥協」することで、自分の中に心理的なゲームをつくり出していないだろうか?
「妥協」ではなく、お互いの価値観を尊重し、「調和」を生み出すことが大切です。
現在受付中の説明会・セミナー情報
- 新入社員コミュニケーション1日研修 ─コーチングのスキルで学ぶ 報連相力アップ─
- 縦割り組織に悩む経営者・組織開発、人事担当者の皆様へ!「グループコーチングWA」体験会のご案内
- 【開催無料・中小企業経営者限定】できる経営者が選ぶ“壁打ち” エグゼクティブコーチング解説セミナー
- 人生が輝きだす最強のコミュニケーション術 無料講座
- 超入門初級コーチングいろは1DAY(10:00-17:00)セミナー
- ビジネスリーダーのための傾聴1DAYセミナー
- 1on1がうまくいかない・・なんとかしたいと思っているあなたへ上司として自信を取り戻す1on1スキル向上セミナー
- 【2026年2月】コーチング経営アカデミー コーチ養成講座説明会
- 【無料開催・経営者・人事担当者限定】これで会社を変える!社員の自律と成長を促すコーチング活用セミナー