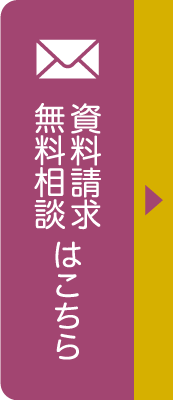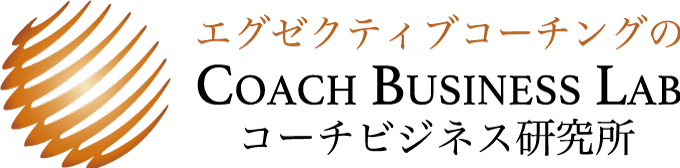バベルの塔の再現。シンパシータワートーキョーの建設は、やがて我々の言葉を乱し、世界をばらばらにする。ただしこの混乱は、建築技術の進歩によって傲慢になった人間が天に近づこうとして、神の怒りに触れたせいじゃない。各々の勝手な感性で、言葉を濫用し、捏造し、拡大し、排除した、その当然の帰結として、互いの言っていることがわからなくなる。喋った先から言葉はすべて、他人には理解不能な繰り言になる。独り言が世界を席巻する。大独り言時代の到来。
第170回芥川賞受賞作『東京都同情塔』より/文藝春秋2024年3月号
『東京都同情塔』でコーチングが想起された…
冒頭、九段理江さんの『東京都同情塔』の書き出し(最初の段落)を引用してみました。選評に目を通すと、多くの選者が高く評価しています。毎回の芥川賞については、掲載される文藝春秋(月刊)を手に取るのが習慣になっているので、今回もそれに倣ったのですが、『東京都同情塔』の主人公である、牧名と拓人の会話が、とても独創的(非現実的?)で、それもあって、対話が核となる「コーチングとは?」を深く考える糸口を与えてくれた、との気づきを得ています。
文学賞には、芥川賞以外にさまざま存在します。ただ芥川賞は、純文学(この言葉の定義も流動化しているように感じますが)を志向する作家の登竜門として、長い歴史を有しています。また一出版社である(株)文藝春秋の思惑を超え、日本の多くのマスコミが取り上げることもあり、注目度が抜群に高いのですね。
そして、「どうしてこの作品が選ばれたのか?」についても、公開されています。9名の選考委員一人ひとりの「選評」が『文藝春秋』に掲載されますから、選者の力量も試される、という側面をもつ文学賞でもあります。
小説家は時代の変化に敏感であり、その情況を見事に言語化してくれます。さらに、九段さんはマジックレアリズムをまぶしている印象です。幻想小説は純文学ではない、という価値観が日本の文壇には存在している(ように感じる)ので、その視点からも芥川賞に選出された『東京都同情塔』は、ユニークな作品と解釈できそうです。
この小説は、「日本語がカタカナ語に変換される不思議(違和感)」の究明に挑む、九段理江さんの姿勢(批評性)が濃厚に表れています。今回のコラムは、このあたりに着目して語ってみることにします。一方で、英語が日本語に翻訳されないまま使われるケースについても、思いを巡らせてみました。
まずは、選評全体のなかの『東京都同情塔』に関する、各選考委員の最初のところを引用させていただきます(9氏のうち5氏の選評)。日本を代表する作家の文体にも触れることが出来て、とても勉強になりますね。
選考委員は『東京都同情塔』に高い評価を与えています
(島田雅彦)
『東京都同情塔』は生成AIとその基盤である大規模言語モデルに対する批評意識を中心に据え、現実を大いに反映した脳化社会のディストピアに生きる憂鬱を語った作品である。……
(松浦寿輝)
「東京都同情塔」に出てくる生成AIの言語には、徹頭徹尾「人間そっくり」だが、同時に徹頭徹尾「非人間的」でもあるという怖さがある。……
(吉田修一)
「東京都同情塔」アンビルトの女王と呼ばれた建築家ザハ・ハディドの国立競技場が完成し、理想主義者の塔が建つ東京が舞台。ある意味、傷つかなかった東京を描くことで、現実に傷ついた東京を浮かび上がらせる。……
(川上弘美)
「東京都同情塔」の作者も、書きながら、いろいろ、考えたのだろうな、と思いました。なぜなら、小説の言葉が、文章が、読者である私に、よかったら、いろいろ考えてみて、と語りかけてくるからです。……
(堀江敏幸)
九段理江さんの「東京都同情塔」は、作品自体の構造計算をめぐる発語をAIという機械(machina/牧名)に委ねる着想に支えられている。ザハ・ハディドの国立競技場と東京都同情塔。二重の仮定の上に立つ一対の世界には、鉄筋コンクリートの重さがない。……
ところで「東京都同情塔」という6つの漢字を重ねた熟語は、この小説が発表されるまで、世界中の誰一人として思い浮かべた人はないだろう、と想像します(断言してもよいと考えます)。極めてキャッチ―なこのタイトルはどのように生み落とされたのか…興味が湧いてきますね。
「シンパシータワートーキョー(仮称。竣工式前後に一般投票により正式名称決定予定)指名設計競技要項」の下に、「新形態刑事施設建設計画有識者会議」の署名がある。密に並んだ文字を解読しようとして分解しようとしたが、途中でくらっとして熱が出そうになる。画面の下からメールのタイトル、「STTコンペの件」が、連続でポップアップ通知される。
「結局、牧名さんが建てるの? シン──」と僕は言いかけて、並べられたカタカナを、
「東京都同情塔」と言い直している。瞬間的に同時通訳者にでもなったみたいに。
「え?」
「東京都、同情塔」僕は丁寧に発音する。他に適切な訳語が思いつかない。
「それ、君が考えたの?」
「うん」
「今? この場で?」
「今、この場で。一般にはまだ公表されていないよね、これ。Twitterでは大体『御苑タワー』って呼ばれているみたいだけど。あと、『新宿タワー』と、『ミゼラビリスタワー』もあったかな」
この箇所は、文藝春秋3月号の270~351ページ(上下2段の全82ページ)に全文掲載された『東京都同情塔』にある牧名と拓人の会話(305ページ)です。作品の前に「受賞者インタビュー(264~269ページ)」も掲載されており、そこで創作秘話が九段さんの言葉で語られます。
「東京都同情塔」が下りてきた……
──作中で牧名が「東京都同情塔」の韻に興奮する場面もありますが、ここまで固い(うまい)韻を踏んだタイトルもないように思います。
九段 : 下りてきたときはすごかったですよ。まさに作中の牧名のようでした(笑)。執筆の序盤のほうで思い浮かんだのですが、この固い韻を世に出すためにも、絶対に最後まで書かなくては、と思いました。このタイトルを発表したい、私の固い韻を見て! みたいな(笑)。
「私の固い韻を見て!」は、牧名ではなく、15歳年下の“新しい友人”である拓人に語らせるという“技”を九段さんは使っていました。拓人は、280ページから登場します。登場人物は、基本的にこの2人のみです。この箇所はト書を廃し「……」と「……」だけでつながっていく会話のパターンです。もう少し交わされます。
ただし、九段さんはこの小説の「書き出し」で、「喋った先から言葉はすべて、他人には理解不能な繰り言になる。独り言が世界を席巻する。大独り言時代の到来」と、言葉にしています。この「批評的コンセプト」を貫くように、この箇所以外の二人の会話は「……」と「……」の間に、多くの字数を使ったト書や「独り言(自問自答)」が挿入されており、「会話していても会話しているイメージが伝わってこない“不思議な小説”を世に送り出したなぁ…」と、私は感じました。コーチング脳になっている“私固有の”解釈かもしれませんが(笑)
そして、15歳年下の拓人と牧名の関係も、現代的かもしれませんね。313ページに1ページにわたって牧名の独り言のような長広舌の言葉が綴られます。その一部を引用します。
…… そんな世界で君みたいな綺麗な建築を見つけるとね、人間はここまで美しくなれるんだって、希望を持つことができる、この弱い私は。君が思っている以上に、私は君から力をもらっている。それに対する対価を、きちんと支払いたいと思う。食事をご馳走するだけじゃなく、もし君が望むなら、現金を渡したいとも思っている。メンテナンスに相応の費用を要するのは、建築も人間も同じでしょ。さっき、ホテルの部屋で、君が私に触ってくれて嬉しかった。もっと君が私に近づいて、もし私の中に入ってくるようなことがあれば、きっと天にも昇る気持ちになるでしょうね。……
最初に引用した「書き出し」に目を転じてみてください。「各々の勝手な感性で、言葉を濫用し、捏造し、拡大し、排除した、その当然の帰結として、互いの言っていることがわからなくなる」という記述が目に留まります。この小説の大きなテーマです。九段さんは、「シンパシータワートーキョー」を「東京都同情塔」に変換させたように、「カタカナ語」がやたらに使われ氾濫している現状を、「互いの言っていることがわからなくなる」と言います。しつこいほどの言語化を試みます。
カタカナ語の氾濫 ≒ 互いの言っていることがわからない…?
数年前に東京で独立したとき、建築仲間たちから国際コンペでも通りがいいようにと「サラ・マキナ・アーキテクツ」を強く推されていなかったら、事務所の名前も普通に「牧名沙羅設計事務所」にしていただろう。カタカナを書く機会を不用意に増やしたくない。
母子家庭の母親=シングルマザー。配偶者=パートナー。第三の性=ノンバイナリー。外国人労働者=フォーリンワーカーズ。障害者=ディファレントリー・エイブルド。複数性愛=ポリアモリー。犯罪者=ホモ・ミゼラビリス。……ずさんなプレハブ小屋みたいなその文字たちを、冷やしたミネラルウォーターに浮かべて口の中で転がしてみる。
このような記述が随所に登場します。
一例として、牧名が仕事に取りかかる前のルーティン(ロングヴァージョン)のシーンを引用します。
ピラティス→ビョークの「カム・トゥー・ミー」をフルコーラス歌唱→座禅を組みエロチックな妄想を膨らませる→妄想を抑圧するための太陽礼拝三周→オリジナルのマントラをゆっくり八回唱える。「私は弱い人間です。私は私の弱さを知っています。私は私の欲望を完全にコントロールできます。私を動かすものは常に私由来の意志であり、私は私の言葉、行動すべてに、責任を取らなくてはいけません」。呼吸を整え、今日も仕事ができますようにと強く念じてスケッチブックを広げる。空白に全神経を集中する。
けれど、頭に浮かんでくるのは依然言葉だけだった。仕方なく、脳内のゴミを掃き出すように文字を書き出していく。浮浪者=ホームレス。育児放棄=ネグレクト。菜食主義者=ヴィーガン。少数者=マイノリティ。性的少数者=セクシャル・マイノリティ。自分の手から書かれたとは信じたくないような文字に、辟易する。
日本で「コーチングの“本質”」は理解されているのだろうか?
「coaching」は米国で誕生し、世紀の変わり目のタイミングで、日本に輸入されました。オリジナルは米国ということもあってか、今日に至るまで、カタカナの「コーチング」が、日本に流通しています(翻訳された日本語は…どうも存在しません)。
一方で、「ing」を付さない「スポーツ・コーチ」の方は、敵性語が解禁された戦後すぐに、独自のニュアンスを伴った「カタカナ語」として、日本に定着してしまいました(根性論と融合して…)。もちろん、現代ニッポンでは、「スポーツ・コーチ」の概念も「コーチング」が組み込まれるようになっていますが…
五十嵐代表は「日本にコーチングを広めたい」というミッションを掲げています。(株)コーチビジネス研究所は、その「志」が原動力です(設立10年を迎えました)。ただ、米国のように7割の経営者にプロコーチが付いているという情況と、日本の違いはどこにあるのか…という問題意識のもと、一昨年8月より、infoサイトの「CBLコーチング情報局」が開設され、日々「コーチング大百科」は更新されています(4月3日時点で415話)。以下はその「わたしたちについて」です。
このたび「コーチング情報局」を開設しました。
コーチングについては、日本にこのことばが輸入される1990年代以前に、ingを付さない「コーチ」ということばがスポーツ界を中心に浸透していました。東洋の魔女の大活躍、金メダル獲得によって「コーチの厳しい指導に耐え抜いた者か栄冠を勝ち取る」というイメージが付与されことは否めません。
もちろん、昭和から平成、そして令和と時代が移ろうに従い、コーチ像も変わってきています。ただし外来語のコーチングをそのまま導入したこともあって、日本においては、その本質が十分に伝わっていないのが実態ではないか… と感じるところです。
コーチングは、人と人が関わり合う社会にとってなくてはならないコミュニケーションの基盤であり、その本質は「受容と共感」に基づく相互理解です。
私どもはこの「CBLコーチング情報局」を通じて、コーチングの本質が一人でも多くの人に広がり浸透していくことを願っています。
小川洋子さんの選評を最後に引用させていただきます
今回のコラムの最後に、選考委員である小川洋子さんの選評を引用させていただきます。他の選者とは少し違っています。少し“ホッ”としています。
(小川洋子)
ある事柄に名前が付く。トランスジェンダー、フェミニズム、多様性……。するとそれまで薄ぼんやりしていた世界の一部が不意に輪郭を持ち、見えているようでいなかったものの存在を意識できるようになる。自分の視界が深まったかのような錯覚に陥り、その言葉を便利な道具として使ってしまう。やがて言葉は膨張し、それを共有できない者を、容赦なく分断してしまう。
「東京都同情塔」は、そうした言葉のいびつさが招く恐ろしさを描いている。共感の行き着き先には、犯罪者に同情を寄せるための塔が建設される。しかもザハ・ハディドが設計した国立競技場から産み落とされる、という形で。
ただ、どうしても私は、建築家の牧名沙羅にも、塔で働く拓人にも人間的な息遣いを感じることができなかった。思考のための言葉ではなく、心からにじみ出てくる声なき声を聞きたかった。
九段さんが小説の可能性を押し広げてゆく書き手であるのは間違いない。そのエネルギーに敬意を表したい。
坂本 樹志 (日向 薫)
現在受付中の説明会・セミナー情報
- 新入社員コミュニケーション1日研修 ─コーチングのスキルで学ぶ 報連相力アップ─
- 縦割り組織に悩む経営者・組織開発、人事担当者の皆様へ!「グループコーチングWA」体験会のご案内
- 【開催無料・中小企業経営者限定】できる経営者が選ぶ“壁打ち” エグゼクティブコーチング解説セミナー
- 人生が輝きだす最強のコミュニケーション術 無料講座
- 超入門初級コーチングいろは1DAY(10:00-17:00)セミナー
- ビジネスリーダーのための傾聴1DAYセミナー
- 1on1がうまくいかない・・なんとかしたいと思っているあなたへ上司として自信を取り戻す1on1スキル向上セミナー
- 【2026年1月、2月】コーチング経営アカデミー コーチ養成講座説明会
- 【無料開催・経営者・人事担当者限定】これで会社を変える!社員の自律と成長を促すコーチング活用セミナー